ドラマ「「独孤伽羅」「独孤皇后」にも登場する独孤伽羅(どっこ から)は、中国の歴史に確かに実在した人物です。
隋(ずい)を建国した皇帝・楊堅(ようけん)の正妻でした。文献皇后とも呼ばれ、夫の楊堅と一緒に「二聖(にせい)」と呼ばれるほど、国の政治に大きな力を持っていました。
この記事では、そんな実在した独孤伽羅がどんな人物だったのか生涯や有名なエピソード(なぜ側室を許さなかったのか、など)を分かりやすくお話しします。
独孤伽羅が実在した証拠
独孤伽羅は架空の人物ではなく、歴史上実在した人物です。
なぜそう断言できるのでしょうか? その一番の証拠は、古い歴史書に彼女の記録がしっかりと残っているからです。
特に重要なのが、『隋書(ずいしょ)』という、隋の出来事を記した公式な歴史書です。
この本には皇帝である夫・楊堅を支え、皇后として政治にも深く関わった独孤伽羅(文献皇后)の生涯や詳しい行動が記録されています。
歴史書に記された独孤伽羅の生涯
独孤伽羅は西暦544年(または553年)に生まれ、602年に死去した人物です。名前は伽羅(から)。死後、文献皇后(ぶんけんこうごう)の称号(諡)が贈られました。
父は北周王朝で大司馬(軍の最高司令官)を務めた独孤信(どっこ しん)です。独孤氏は代々軍事を司る有力な家柄でした。
伽羅は独孤信の七女として誕生。将来性を見込まれ、後の隋の初代皇帝となる楊堅(ようけん)に嫁ぎました。
楊堅はその後、北周の重臣として権力を確立し、西暦581年に北周の静帝から禅譲(ぜんじょう)を受けて隋王朝を建国し、皇帝に即位します。
歴史書によれば、この楊堅の即位に際し独孤伽羅は楊堅を強く促したと伝えられています。
楊堅が皇帝に即位すると、伽羅は皇后となり楊堅とともに政治の実務に深く関与しました。このため、夫婦並んで「二聖(にせい)」と呼ばれるようになります。
夫とともに「二聖」と呼ばれた理由~政治への深い関わり~
独孤伽羅が夫の皇帝・楊堅と並んで「二聖(にせい)」と呼ばれたのは、彼女が皇帝とともに政治の意思決定に深く関わったからです。
歴史書によると楊堅は重要な政務について決断を下した後、その内容を宦官(かんがん)を通して独孤伽羅に報告させていたといいます。
伽羅は報告を受けると楊堅の決定が適切かどうかを判断し、必要であれば意見を言いました。楊堅は伽羅の意見をしばしば聞き入れ、政治に反映させました。
彼女の政治にへの考え方や姿勢を示すエピソードがいくつか残っています。
独孤伽羅の義兄弟である崔長仁(さい ちょうじん)が重罪を犯した際、楊堅は皇后の親戚であることから罪を軽くしようとしました。しかし伽羅はこれに対し、「国家のことは私(皇后)に遠慮してはいけません。法に従って厳正に対処すべきです」と主張しました。その結果、崔長仁は法通りに処刑されました。これは、彼女が個人的な情よりも国家の法を重んじた一例です。
一方、独孤伽羅の異母弟・独孤陀(どっこ だ)が、皇后を呪詛した疑いで捕らえられ楊堅が激怒して処刑を命じた際には、伽羅は楊堅に嘆願しました。
彼女は「陀がもし政治を歪めて民を苦しめたのであれば何も申しません。しかし、これは私の個人的な問題ですので、どうか命だけはお助けください」と訴えたといいます。この嘆願によって独孤陀は死罪を免れました。これは、公私を区別し個人的な問題には情けをかける一面を示しています。
独孤伽羅は読書を好み、歴史や政治に関する知識を深めていたと考えられます。また普段の生活は非常に質素であったと伝えられており、皇后としての立場にふさわしい品行を保とうと努めていた様子がうかがえます。
独孤伽羅は単に皇帝の妻として後宮にいるだけでなく、夫とともに政治の判断に関わり、時には皇帝の決定を左右するほどの強い影響力を持っていました。
こうした皇后の存在が、楊堅と並んで「二聖」と称される理由になりました。
嫉妬深い皇后? 側室禁止令と衝撃のエピソード
独孤伽羅は夫の楊堅が他の女性を側室にすることに非常に厳しかったことが歴史書に記されています。そのため嫉妬深い皇后と言われることもあります。
特に夫の楊堅(ようけん)が自分以外の女性に目を向けるのを、とても嫌がりました。
彼女は基本的に楊堅が側室を持つのを許しませんでした。ただ、戦などで身寄りがなくなった女性だけは、特別に宮殿に置くのを許したそうです。
ですが、楊堅も密かに他の女性を可愛がろうとすることがありました。
ある時、楊堅は北周の武将だった尉遅迥(うっち けい)の孫娘をとても気に入ってしまいます。とても美人だったようです。
でもそのことは独孤伽羅にバレました。すると伽羅は、ひそかにこの女性を宮殿の外に連れ出して殺害してしまった言われています。これはとても衝撃的な話ですね。
これを知った楊堅は、激しく怒り馬に乗って宮殿を飛び出して、近くの山に隠れてしまいました。
「私は皇帝なのに、なんでこんなに自由がないんだ!」と嘆いたそうです。まるで誰が皇帝か分からないくらいだったんですね。
皇帝がいなくなり家臣たちはこまりました。高熲(こうけい)たちが楊堅を一生懸命説得して、やっと宮殿に戻ってもらいました。
楊堅を心配していた伽羅は、彼を連れ戻してくれた高熲に泣いてお礼を言ったといわれます。
伽羅の厳しい態度は楊堅に対してだけではありませんでした。他の臣下たちが、正妻以外に女性を持つことにも厳しかったのです。そういう人がいると聞くと楊堅に言ってその女性を遠ざけさせたり、その臣下を遠ざけたりしたと言われています。
たとえば楊堅を説得した高熲が、妻を亡くした後に別の女性をそばに置いたことも、伽羅が高熲を嫌うようになった理由の一つと言われます。
独孤伽羅は夫の側室を認めず、そのためには激しい行動に出ることもありました。彼女の情熱的で厳しい性格がよくわかります。
皇太子・楊勇の廃位と独孤伽羅の影響
楊堅と独孤伽羅の間にはたくさんの子供がいましたが、長男の楊勇(ようゆう)が皇太子になっていました。
楊勇には何人もの側室がいました。でも正室の元氏(げんし)をあまり大切にしなかったようです。
ある時、正室の元氏が病気で亡くなってしまいます。独孤伽羅は楊勇の側室の一人、雲昭訓(うんしょうくん)が、元氏を殺したのではないかと疑いました。
この出来事があってから独孤伽羅は皇太子・楊勇をひどく嫌うようになり、代わりに次男の楊広(ようこう)をかわいがるようになりました。
夫の楊堅も、もともと楊勇の態度があまり気に入っていませんでした。独孤伽羅は、そんな楊堅に楊勇を皇太子の位から下ろすことを強く勧めました。
そして西暦600年、楊勇は皇太子の位を奪われてしまいます。
代わりに独孤伽羅がかわいがっていた楊広が新しい皇太子となりました。独孤伽羅の思いが次の皇帝を決めることに大きな影響を与えた出来事でした。
独孤伽羅の死、そして息子・煬帝と隋の滅亡
西暦602年。独孤伽羅は永安宮(えいあんきゅう)で亡くなりました。夫での楊堅より、少し早い旅立ちでした。
伽羅が亡くなった後、西暦604年に彼女が皇太子にした息子、楊広(ようこう)が次の皇帝となりました。後に『煬帝(ようだい)』と呼ばれる人物です。
しかし、煬帝は大きな戦争(高句麗遠征など)を何度も行ったり、運河を作る大きな工事をしたりしました。
これらの無理なやり方が多くの人々を苦しめ、国中に反乱が起きる原因となってしまったのです。
反乱が広がる中で煬帝は家臣に殺されてしまいます。
その後、孫の楊侑(ようゆう)が皇帝になりますが、隋の重臣だった李淵(りえん)に位を譲る形となり、隋という国はわずか一代(実質二代)で滅びてしまったのです。
隋が早くに滅んでしまったのは、煬帝のやり方に問題があったからだと言われています。そして、その煬帝を皇太子にするよう強く勧めたのが、母である独孤伽羅でした。
もしかすると、これが彼女の最後の、そして最大の判断ミスだったのかもしれません。
ちなみに隋に代わって『唐(とう)』を作った李淵の母は、独孤伽羅の姉ににあたる人物でした。これもまた、不思議な縁を感じる話ですね。
独孤伽羅の姉はドラマ「独孤伽羅」では「獨孤曼陀」の名前で登場します。
独孤伽羅の子どもたち
独孤伽羅と夫の楊堅の間には、たくさんの子供たちがいました。歴史書によると五人の男子と三人の女子がいたようです。
男の子たちは、それぞれが様々な道を歩みました。
- 楊勇(ようゆう): 長男。一度は皇太子になりましたが、後に廃位されました。
- 楊広(ようこう): 次男。母の伽羅に深くかわいがられ、後に二代皇帝 煬帝となりました。
- 楊俊(ようしゅん): 三男。秦孝王(しんこうおう)と呼ばれました。
- 楊秀(ようしゅう): 四男。蜀王(しょくおう)。楊広が皇太子になった後、過去の罪を理由に官位を剥奪され幽閉されました。
- 楊諒(ようりょう): 五男。漢王(かんおう)と呼ばれました。容態の時代に反乱を起こしましたが、失敗して位を追われました。
- 楊麗華(ようれいか):長女。楽平公主(らくへいこうしゅ)。北周の宣皇帝 宇文贇の皇后になりました。北周を滅ぼした父を深く憎んだと言います。
独孤伽羅と楊堅の子どもたちは、このようにそれぞれが様々な人生を歩みました。彼らの存在も、隋の歴史に深く関わっていくことになります。
ドラマ「独孤伽羅」と史実の違い
独孤伽羅という名前を、中国ドラマで知った方も多いと思ます。
ドラマ『独孤伽羅〜皇后の願い〜』(原題:独孤天下)では独孤三姉妹が「天下をとる」という大きなテーマで描かれているのが特徴です。ドラマのタイトルや劇中でも「天下」という言葉がよく出てきますね。
このドラマでは長女・独孤般若(どっこ はんにゃ)、次女・独孤曼陀(どっこ ばんだ)、そして三女・独孤伽羅のそれぞれの人生が隋が建国されるまでの北周(ほくしゅう)の時代を中心に丁寧に描かれています。ドラマの始まりに北周の初代皇帝、宇文覚(うぶんかく)が登場するのは史実通りです。
でもは史実との違いもいくつかあります。
まず、『独孤三姉妹が自ら天下をとる』というのはドラマ独自の解釈です。史実では彼女たち自身が直接天下を支配しようとしたわけではなく、夫や息子が皇帝になることで、大きな力を持つ家柄となった、という方が正しいです。
ドラマの中で、北周の実力者だった宇文護(うぶんご)が登場しますが、ドラマでは若く描かれ、長女の般若と特別な関係になったりと物語上のキャラクターとして大きくアレンジされています。
史実では宇文護は伽羅や楊堅よりずっと年上で、そのような関係の記録はありません。悪役だけど憎めない存在として描かれているのは、ドラマならではですね。
また楊堅と伽羅の娘である楊麗華(ようれいか)が、ドラマでは宇文護と般若の娘という設定になっているのも史実とは違います。楊麗華は楊堅と伽羅の間に生まれた子供です。
次女の曼陀が、後の唐の建国者・李淵(りえん)の母になる(元の記事で触れた独孤伽羅のお姉さんにあたる元貞太后ですね)までの人生が描かれ、その嫁ぎ先である李家の物語が描かれるのは、史実に基づいた部分を膨らませていますね。
ドラマが隋が建国されるあたりで終わるのも、三姉妹のそれぞれの道のりが一つの区切りを迎えるとして、分かりやすい終わり方と言えるでしょう。
このように、ドラマは歴史を参考にしながらも、フィクションの要素を加えて面白く作られています。華やかなドラマを見て独孤伽羅に興味を持ったら、ぜひこの記事でご紹介したような歴史書(『隋書』など)の内容にも触れてみて、独孤伽羅の本当の姿を探求するのも面白いかと思います。
まとめ:歴史に名を残す文献皇后
この記事では独孤伽羅(どっこ から)が実在の人物であること、そしてその生涯をたどってきました。
彼女は隋を作った皇帝、楊堅(ようけん)の正妻で「文献皇后(ぶんけんこうごう)」と呼ばれました。
皇后というだけではなく、夫の楊堅とともに「二聖(にせい)」と呼ばれるほど国の政治に深く関わりました。
側室を許さない厳しい一面や、皇太子選びへの影響など、その個性的な人柄や判断は、良くも悪くも歴史に大きな足跡を残しました。
ドラマの独孤伽羅
独孤伽羅・皇后の願い(原題:独孤天下) 2018、中国、演:胡冰卿(フー・ビンチン)
独孤皇后 2019、中国、演:陳喬恩(ジョー・チェン)
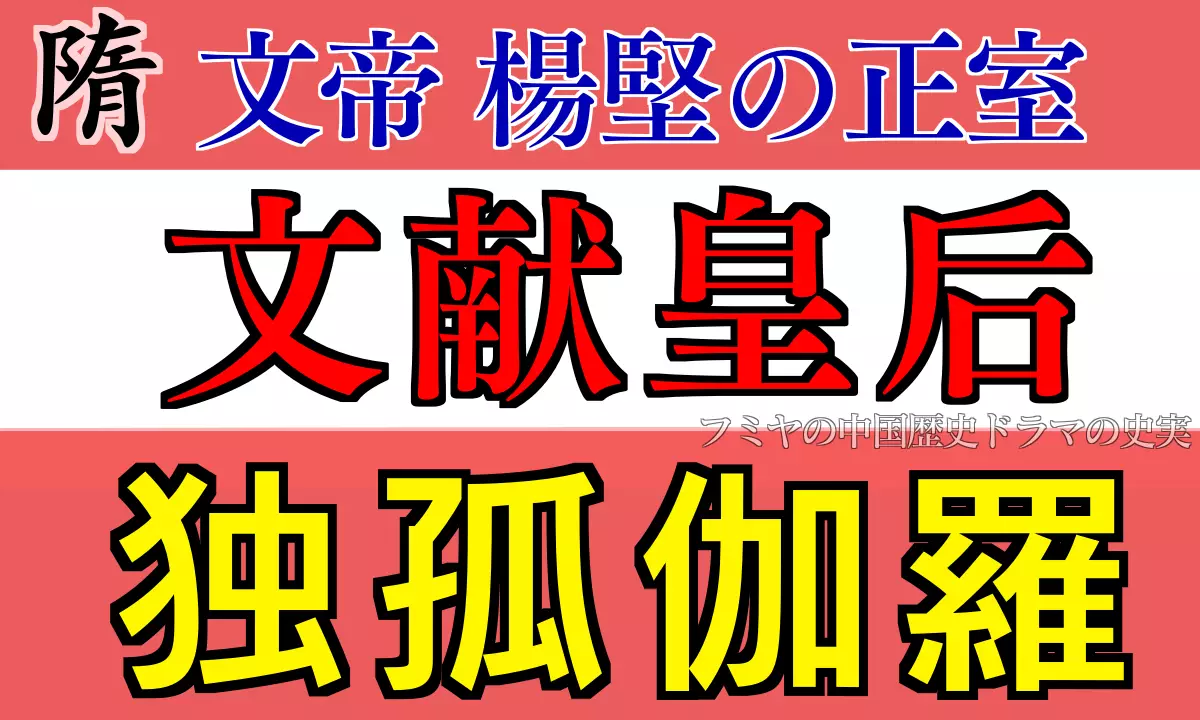
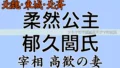
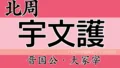
コメント