清朝ドラマや小説には「エホナラの呪い」という言葉が出てきます。葉赫那拉氏(エホナラ氏)の女性が清朝を滅ぼすという伝説です。多くの作品ではドラマチックに描かれていますよね。
でも史実としては「エホナラの呪い」は存在しません。
この記事ではなぜ「エホナラの呪い」が誕生したのか?なぜ広まったのか?歴史とはどう違うのかをわかりやすく解説します。
葉赫那拉氏(エホナラ)の呪いとは?
清朝ドラマや小説で時折登場する「エホナラの呪い」とは、葉赫那拉氏(エホナラ氏)出身の女性が清朝の運命に関わるという伝説です。
エホナラの呪いの大まかな内容は次の通りです。
- かつてヌルハチが女真を統一するとき、最後まで激しく抵抗したのがイェへ部(葉赫那拉氏の本拠)の最後の首長 ギンタイジだった。
- ギンタイジは死の間際に「清朝の一族にたとえ女一人でも葉赫那拉の人間が加われば、その者がおまえ(ヌルハチ)の一族を滅ぼすだろう」と呪いの言葉を残した。
- そのため清朝では葉赫那拉氏の女性を后妃にするのを避ける掟があった。
- 清末の咸豊帝がこの掟を破って葉赫那拉氏の女性を妃に迎えた。
- その結果、その女性が西太后となり清朝の権力を握り滅ぼした。
というのが「葉赫那拉(エホナラ)の呪い」の物語です。
この伝説は現代の小説やドラマでもよく取り上げられていますが、実際の史実ではありません。ギンタイジはそんな呪いは残していませんし、葉赫那拉氏の妃は何人もいます。
あくまで物語の演出です。
呪いの出所と歴史的検証
史実でないなら「エホナラの呪い」はどこから出てきたのでしょうか?
どうやら清朝末期から中華民国時代に誕生したようです。
惲毓鼎の『崇陵伝信録』1912年
確認できる一番古い「エホナラの呪い」は1912年に清朝の役人 惲毓鼎(ウンイクテイ)が書いたもの。惲毓鼎は彼が光緒帝を慰めるために書いた『崇陵伝信録』という回顧録では。
ヌルハチによってイェヘ部の男がほとんどいなくなるほど殺された。このときイェヘ部の首長は「我が子孫に女子が一人でも残るなら、必ずや満洲を滅ぼす!」と呪いをかけた。それ以来、「宮廷では葉赫氏の女性を選ばないという祖法があった」と紹介しました。
でも実際にヌルハチがイェヘ部に勝ったのは事実ですが、イェヘ部を皆殺しにはしてませんし、そのような掟もありません。惲毓鼎が人目をひくためにでっち上げた嘘なのです。
蔡東藩の『清史演義』 1917年
中華民国時代の 1917年に蔡東藩が書いた小説『清史演義』には、石碑に「建州(ヌルハチの勢力)を滅ぼす者は葉赫」と記されていたという話や、葉赫部の首長ギンタイジが呪いを残したと書かれています。当時の満洲語、漢語、朝鮮語のどの史料にも書かれていません。『崇陵伝信録』から引用された可能性が高いです。
徳齢の『瀛台泣血記』1930年
西太后に仕えた女官・徳齢が民国時代に書いた本。この中でも赫那拉氏の者が死の間際に「いつか葉赫那拉の子孫が、ヌルハチの子孫に復讐する」と呪いの言葉を残したという話が記されています。これも徳齢が小説に影響を受けたか、想像で書いたものです。
このように、確かな記録ではなく。清朝が滅亡したことを悲しむ個人の主観や小説に書かれたものばかり。エホナラの呪いの事実を証明する根拠はないのです。
葉赫那拉氏と清朝の実際の関係
歴史上の葉赫那拉氏と清朝はどのような関係でしょうか?
なお、中国語ではエホナラと発音しますが、満洲語ではイェヘナラと発音します。以後、歴史上の人物の名前はイェヘナラと書きます。
イェヘナラ(葉赫那拉)氏は女真の有力な部族でした。一族の中にはナラ(納喇)、ナーラン(納蘭)氏と姓を変えた家もありますが。イェヘナラ氏の一族として扱われます。
史実ではイェヘ部が最後までヌルハチに抵抗して敗北したのは事実ですが。イェヘ部は全滅してませんし。ヌルハチやその後継者たちが葉赫那拉氏を避けた記録もありません。そればかりか葉赫那拉氏(イェヘナラ氏)は清朝と深く関わっています。
- ヌルハチの妻モンゴジェジェはイェヘ部出身。
- モンゴジェジェはホンタイジの母。
ヌルハチには生涯で4人の妻がいましたが3人目の妻モンゴジェジェはイェヘ部出身です。ホンタイジが産まれたのがイェヘ部が敗北するより前ですが、だからといってホンタイジが冷遇されたわけでもなく。次の皇帝になっています。モンゴジェジェの妹もヌルハチの側室になっています。
その後の皇帝たちにもイェヘナラ氏の女性が妃になっています。
- 2代 ホンタイジ
- 側妃イェヘナラ氏
- 康煕帝
- 貴人ナラ(納喇)氏(那丹珠の娘)
- 貴人ナラ(納喇)氏(昭格の娘)
- 乾隆帝
- 舒妃イェヘナラ(葉赫那拉)氏
- 道光帝
- 和妃ナラ(納喇)氏
- 咸豊帝
- 懿貴妃(慈禧太后・西太后)イェヘナラ(葉赫那拉)氏
- 璹嬪 イェヘナラ(葉赫那拉)氏
- 玉嬪 イェヘナラ(葉赫那拉)氏
- 光緒帝
- 孝定景皇后(隆裕太后) イェヘナラ(葉赫那拉)氏
他にも康煕帝に仕えた重臣 スクサハや、ナーラン・ミンジュもイェヘナラ氏出身です。とくにミンジュはギンタイジの孫ですから、呪いが本当なら重臣にするはずがありません。
イェヘならとその分家はウラナラやニオフルほど大きな勢力はなかったものの、満洲八旗のひとつで皇帝直属の部隊 正白旗を構成する一族として皇帝を支え続けました。
清朝の歴代皇帝は葉赫那拉氏を恐れて避けることはありませんでした。何人もの妃嬪が誕生し、一族の者も皇帝に仕えています。
なぜ「エホナラの呪い」が広まったのか
ではなぜ事実ではない「エホナラの呪い」が広まったのでしょうか?それには清朝末期の複雑な歴史的や文化的な要素が関係しています。
この伝説の広がりには、以下の理由があります:
- 歴史の責任を女性に転嫁するため:清朝が滅亡したのは王朝組織の腐敗や時代の変化についていけなかったこと、外国勢力の外圧にたえられなかったことなど。複雑な原因があります。でも複雑でわかりにくい問題ではなく権力を握った西太后や隆裕太后のせいにすることで、男性支配層の責任を回避できると考えられました。
- ドラマチックな物語性:「少数勢力でも歴史を動かせる」というドラマチックな要素は、ドラマや小説にとって格好の題材でした。特に「エホナラの呪い」という言葉自体がインパクトがあって視聴者や読者の興味を掻き立てます。
- 文化的な連想:「エホナラの呪い」に影響を与えたのは中国古典『史記』に書かれた故事「楚虽三戸,亡秦必楚」と思われます。これは秦末期の混乱の様子を描写するときに使われた言葉ですが「秦に滅ぼされた楚の者がたった3戸(家)でも秦を滅ぼす」という内容です。少数勢力の残党が強大な国家を滅ぼすという考え方から、エホナラの呪いが生まれ人々に受け入れられたと考えられます。
こうしたことから「エホナラの呪い」は歴史的事実というよりは、エンタメ的なインパクトのあるお話として人々の間に広まったと思われます。
まとめ
「エホナラの呪い」は史実ではありません。ドラマの演出や小説で語られる作り話です。葉赫那拉氏の女性は何人も清朝の後宮にいますし、一族は貴族として活躍しています。清朝の滅亡は呪いではなく、政治的・社会的な要因が重なった結果です。ドラマや小説の描写は史実とは違うというのを意識して楽しむことが大切ですね。
エホナラの呪い関連記事
・如懿伝23・24・25・26話のあらすじとネタバレ
舒妃が登場する場面で「エホナラの呪い」の話題が出ます。

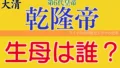
コメント