柔然(じゅうぜん)は謎の多い遊牧民国家です。
5世紀から6世紀にかけてモンゴル高原を舞台に、騎馬の力で広大な領域を支配しました。
北魏と激しく対立し、後の遊牧帝国に影響を与えた彼らは一体どのような人々だったのでしょうか?
この記事ではその読み方から起源、社会、そして「ムーラン伝説」との意外な繋がり、中国ドラマ「後宮の涙」における描かれ方まで、様々な角度から柔然の素顔と歴史を紹介します。
草原に消えた強大な遊牧民の足跡を共に辿ってみましょう。
柔然とは?
柔然の読み方は「じゅうぜん」
まず、この謎めいた遊牧民国家の名前ですが「柔然」の漢字に深い意味はありません。彼らの言葉の発音を漢字に当てはめたものと考えられています。元の言葉がどのような意味だったのかは、残念ながら分かっていません。
「柔然」は(じゅうぜん)と読みます。「にゅうぜん」や「やわらかぜん」などと誤読されることもありますが、歴史を語る上では正確な読み方を覚えておきましょう。
また「魏書」「北史」「南史」なでは「蠕蠕(じゅじゅ)」、「晋書」では「蝚蠕」と書かれますが、これら南北朝時代の史書は敵を侮辱する表現が多く、蠕蠕も差別的な表現。
柔然はいつ頃存在した遊牧民国家なの?
柔然が歴史の表舞台に登場するのは4世紀末から6世紀中頃にかけてです。
具体的には中国の南北朝時代、北魏(ほくぎ)と激しく対立した遊牧民国家としてその名を轟かせました。約200年以上にわたり広大なユーラシア北方の草原地帯で強大な勢力を誇りました。
どこに拠点を置いていたの?
柔然が活動したのはモンゴル高原を中心とする地域です。
この広大な草原を自在に駆け巡り、騎馬民族としての機動力を活かして周辺地域に影響を与えました。
柔然の最大支配範囲は現在の中国北部、モンゴル、ロシア、カザフスタンの一部にまで及ぶ広さでした。
柔然の君主号「可汗(カガン)」
柔然の支配者は「可汗(カガン)」という称号を用いていました。
この称号は王の中の王。他の王よりも上に立つ「皇帝」に相当する称号です。「可汗」は遊牧民の君主号として最も権威のある称号となり、後の突厥やモンゴル帝国へと引き継がれ「ハーン」の語源となりました。
これをみても柔然が遊牧民の歴史で重要な位置な存在なのがわかります。
柔然の社会:移動と自然と共に生きる
柔然の人々は夏は北、冬は南へと季節ごとに移動しながら、狩猟と牧畜を中心とした生活を送っていました。定住民のような城郭を持たず氊帳(てんちょう:ゲル)と呼ばれる移動式の住居に住んでいました。
服装は辮髪が特徴的。錦や革製の短い上着、口の窄いズボン、深い靴、外套を身につけていました。遊牧生活に適した機能的な服装だったと考えられます。
柔然の政治:可汗を中心とした支配体制
柔然の君主は、可汗(カガン)と呼ばれました。皇后は可賀敦(カガトゥン)です。可汗は普通は国の大臣たちによって郁久閭(いくきゅうりょ)氏の中から選ばれました。
普段は部族ごとに分かれ、独自の指導者のもとに生活していました。国家の重要なことは毎年秋に可汗・王侯や部族長たちが集まる会議で決定されます。
可汗という君主は存在しますが、それぞれの民は部族長のもとにあり。独裁的な力を持っていたわけではありません。
柔然の文化・宗教
文化面では自然の精霊や祖霊を崇拝するシャーマニズムや天を崇拝するテングリズムが信仰され、一部には仏教の影響も見られました。
また、他の騎馬遊牧民と同様に柔然も狼をシンボルにしていました。
結婚観:家柄が大切・レビラト婚も
可汗位は郁久閭氏の世襲。婚姻では家柄が重視されました。匈奴や鮮卑と同様に、夫に先立たれた妻は夫の兄弟の妻になるレビラト婚の風習もありました。結婚は氏族の同盟との考えがあったからです。
経済活動:交易による生活の補完
柔然の人々は自給自足の生活が基本ですが、狩猟・牧畜で得られた馬や貂皮などを中国と交易し穀物、綿、漢方薬、書物などを輸入していました。
柔然の歴史
柔然はどのようにして広大な遊牧国家を築き上げ、そしてなぜ歴史の舞台から姿を消してしまったのでしょうか?
柔然の起源:部族連合から強国へ
柔然の祖先は東胡といわれますがよくわかっていません。
4世紀頃、モンゴル高原にいた騎馬遊牧民である鮮卑が南下、華北に幾つかの国を作りました。
その後のモンゴル高原で台頭したのが柔然です。部族をまとめた 郁久閭 社崙(いくきゅうりょ しゃろん)は可汗(かがん)を名乗りました。
彼らはモンゴル高原から東トルキスタンへと進出し、タリム盆地の東西交易路を掌握することで、さらに勢力を拡大しました。
柔然と北魏:草原の覇者と中原の雄、宿命の対立
肥沃な中原を支配する北魏と広大なモンゴル高原を所有する柔然は互いの勢力圏を巡り長い間、激しい対立を繰り広げました。
国境地帯では頻繁に侵攻と略奪が繰り返され、時には大規模な戦いも発生。互いに疲弊しましたが、決定的な勝敗を見ることはありませんでした。
449年には北魏の太武帝による討伐を受け大敗したものの、その後も争いは続きます。
北魏は東魏と西魏に分裂。東魏と西魏は柔然と婚姻関係を結び、可汗の阿那瓌の娘を迎えました。
柔然と突厥: 従属からの逆襲、そして滅亡へ
強大な遊牧帝国を築き上げた柔然でしたが、6世紀に入ると徐々に衰退の兆しが見え始めます。その背景には、いくつかの要因が重なっていました。
まず、内乱や指導者層の弱体化です。可汗の地位を巡る内部の争いが頻発し、国家の統一が揺らぎました。指導者の無能さや贅沢な生活も、国力を疲弊させる大きな原因となりました。
次に、新たな遊牧民族の台頭です。特に、アルタイ山脈方面で勢力を拡大してきた突厥(とっけつ)は、柔然にとって深刻な脅威となりました。もともと柔然に従属していた突厥は、次第に力を蓄え、柔然からの自立を目指すようになります。
柔然の滅亡
552年。可汗の阿那瓌(あなかい)率いる柔然は突厥の土門可汗率いる軍勢に敗北、阿那瓌は戦死。
その後も柔然の残存勢力は抵抗を試みましたが、突厥の勢いを止めることはできませんでした。一部は西方へ逃れアヴァールになったとも伝えられていますが、遊牧帝国としての柔然は滅亡しました。
柔然を滅ぼした突厥は新たな遊牧帝国を築き上げ、東アジアの歴史に大きな影響を与えることになります。
柔然の人々が滅亡後どうなったのか詳しい記録は残っていません。突厥に吸収されたり、周辺の他の遊牧民に合流したりしたと考えられています。
ムーラン伝説と柔然
「ムーラン」はディズニー映画にもなったので聞いたことのある人も多いでしょう。もともとは中国の伝説・木蘭(もくらん)がもとになっています。
ムーランは年老いた父の代わりに男装して戦場へ赴き、数々の手柄を立てて故郷へ帰るという内容。
この有名なムーラン伝説と柔然はどのような関係があるのでしょうか?
ムーラン伝説の概要 – 父の身代わりとなった勇敢な娘
ムーラン伝説は時代によって少しずつ内容が違いますが。一般的には以下のようなストーリーです。
- 徴兵: 北方の異民族が侵攻、皇帝は各戸から一人ずつ兵士を徴集します。木蘭の父は高齢で病弱で、出兵できる兄もいません。
- 決意: 父の身を心配した木蘭は、男装して父の代わりに兵士として戦場へ行くことを決意します。
- 従軍: 木蘭は男性として軍隊に加わり勇敢に戦います。戦いの中で活躍し、多くの功績を挙げます。
- 凱旋: 十数年後、戦いが終わり木蘭は故郷へ戻りました。皇帝は彼女の功績を称え高い位を与えようとしますが、木蘭は辞退して故郷で家族と静かに暮らすことを望みます。
- 正体: 故郷に戻り女性の姿に戻った木蘭を見て共に戦った兵士たちは初めて彼女が女性だったことに気づき驚きます。
中国ドラマで多い男装で戦う女性の始まり
彼女が女性なのを隠し通し、戦場で活躍する姿は多くの人々に感動と勇気を与えてきました。
この伝説は時代を超えて語り継がれ。中国ドラマに男装の女性が多い理由のひとつにもなるほどです。
姓は?
木蘭は最初は姓はありませんでしたが、その後「花」「朱」「木」「魏」などの姓が付け加えられ。京劇では「花木蘭」となっています。
この物語はいつ出来たの?
陳(557-589年)で書かれた『古今楽録』という記録に北魏の『木蘭詩』として登場するのが一番古い記録。
そのため中国の南北朝時代に成立したと考えられています。
木蘭は鮮卑人だった
木蘭は物語なので実在の人物ではありませんが。北魏に伝わる物語だったこと。
モンゴルで発見された鮮卑貴族の女性の遺骨を調べた所。生前は馬に乗り弓矢を使い筋肉が発達していた形跡があること。遊牧民の女性は戦闘に参加することもあったことなどから。
木蘭は鮮卑人社会の話だった。というのは現在の定説です。
柔然との関連 – 伝説の舞台となった時代背景
ムーラン伝説の舞台となったのは北魏が最有力。
そして、この北魏と対立していたのが柔然でした。
伝説の中でムーランが戦った敵として描かれるのは北方の遊牧民です。
具体的な民族名は明かされないことが多いものの、その時代背景や場所を考えると、ムーランの敵役は柔然の可能性が高いのです。
北魏は北方にある強大な遊牧民国家 柔然の侵攻に常に脅かされていました。そのため北魏の男性は常に兵役の義務を負っています。
ムーランが父の身代わりとなる設定もこのような時代背景があってから生まれた物語と言えますね。
敵役としての柔然 – 伝説に彩られた遊牧民のイメージ
ムーラン伝説では柔然(あるいは遊牧民)は、野蛮で侵略的な存在として描かれます。
これは物語が北魏や中華王朝の視点から語られているため、敵対する勢力は野蛮で否定的に描かれるからです。
でも史実の柔然は単なる侵略者ではありません。
独自の文化や社会を持ち、広大な草原で独自の歴史を築き上げてきた民族です。
中国ドラマ「後宮の涙」にみる柔然

中国ドラマ「後宮の涙」で舞台となる北斉は鮮卑族の国です。
ヒロイン・陸貞を愛する皇子・高湛(こうかん)と姉の長公主の母、郁皇后は柔然出身という設定。
異民族の柔然から嫁いだ郁皇后は争いに巻き込まれ毒殺されるという悲劇的な最期をとげます。
異文化で育ったせいかそれとも高湛が単に世情に疎いのかはわかりませんが。高湛が北斉の習慣に疎い一面を見せたり、柔然人に変装したり。劇中で柔然の音楽がでてきたりなど。物語に深みをもたせています。
郁皇后は実在した人物で。柔然可汗・阿那瓌の娘 郁久閭氏 。東魏の高歓と結婚しました。
ただし史実の武成帝 高湛の母は郁久閭氏ではありません。
中国ドラマでは北方遊牧民は野蛮な敵として描かれがちです。
でも「後宮の涙」ではヒロインの重要な相手役となる高湛が柔然の血を引く皇子として登場するのは珍しいです。単なる敵対勢力としてだけでなく、異なる文化を持つ人々との関係やその血を引く人物の葛藤を描こうとする意図が感じられます。
ドラマをより深く楽しむために、敵役として描かれがちな遊牧民にも多様な側面があったこと、そして「後宮の涙」が高湛というキャラクターを通して、そうした視点を取り入れようとしている点に注目してみるのも面白いかもしれません。
まとめ
柔然は4~6世紀にモンゴル高原で活躍した遊牧民族。可汗を君主とし騎馬戦術に優れていました。
北魏と激しく対立する一方、東西交易で栄えましたが内紛や突厥の台頭により552年に滅亡しました。
「ムーラン伝説」では北方の敵として柔然(またはそれに相当する遊牧民)が登場。
「後宮の涙」では、北斉の皇子・高湛の母が柔然出身という設定。単なる敵対勢力ではない多角的な視点を取り入れています。
ドラマを通して歴史上の柔然にも関心を向けてみるのはいかがでしょうか。


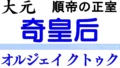
コメント