唐代の詩にも登場する名勝「楽游原(らくゆうげん)」は、長安を見下ろす高台として栄華と黄昏を見届けた地でした。
その地名を冠した中国ドラマ『楽游原』では、戦乱と権力の中で生きる人々が心の平穏を取り戻す象徴の場所として描かれています。
この記事では、史実における楽游原の由来や文化的背景を紹介しながら、ドラマで再解釈された“心の原野”としての意味を詳しく解説します。
楽游原とは? 長安を見下ろす名勝地
楽游原(らくゆうげん/乐游原)は実在する地名です。
現在の陝西省西安市雁塔区に残る黄土の高台で、唐代の都・長安で最も有名な“登高と詩宴の名所”でした。詩人・李商隠が「夕陽无限好、只是近黄昏」と詠んだ場所でもあり、太平公主の華麗な山荘が築かれたことでも知られています。
要点(史実の概要)
- 所在地:陝西省西安市雁塔区。大雁塔の北東に位置する高台。
- 性格:唐代に「登高」「詩会」「遊宴」が行われた文化の中心地。
- 象徴性:「盛唐の黄昏」「栄華と没落」を象徴する詩的舞台。
- 文学的遺産:李商隠、韓愈、杜牧らの詩に詠まれた。
これらの要素から、楽游原は唐代の文化・文学・政治を交差させる象徴的空間だったとわかります。
単なる観光地ではなく、都の知識人たちが季節ごとに登り、詩を詠み、権力や人生を思索する場所だったのです。
地理と時代の背景
唐代の長安は碁盤目状に整備された巨大な都城でした。その南東の外縁にあたる丘陵地帯が、現在の「楽游原」です。長さは約3.5km、幅200〜300m、最高標高は467m。
南には曲江池(詩会と花見の舞台)、西には慈恩寺(大雁塔)、東には青龍寺(空海が学んだ寺)が並んでいました。
『長安志』には
登原四望、宮闕掌中
出典:『長安志』
「その眺望は、都城全体を手のひらに載せるようだ」
と記されています。
この立地が楽游原を「都を見下ろす風流の台地」として特別な場所にしたのです。
春の上巳節、秋の重陽節には人々が登高して詩を詠み、幄幕(テント)が一面に張られ、車馬が行列を成したといいます。
つまり楽游原は唐人にとって「季節と文化を楽しむ舞台」。後世に伝わる“唐の繁栄を象徴する理想的な風景”だったのです。
現代の楽游原
現在もその台地は残り、青龍寺遺址・空海記念碑などの史跡が点在。
一帯は「楽游原歴史文化公園」として整備され、春には十数種の桜が咲き誇る花見の名所として賑わいます。古代の“詩と花の原”がいまも西安市民の憩いの場所として生き続けているのです。
名前の由来 「楽不思帰」と歴史
前漢の皇帝が愛した場所
「楽游原(らくゆうげん)」という名は漢代の皇帝の感動から生まれました。
前漢の第十代皇帝・宣帝(劉詢/りゅうじゅん)がこの地を訪れた際、
あまりの景色の美しさと心地よさに「楽しすぎて帰るのを忘れる(樂不思歸)」と語った、
という逸話が『漢書』や『資治通鑑』に記されています。
その言葉を記念して建てられたのが「楽游廟(らくゆうびょう)」で、この廟に由来して「楽游原」という地名が生まれました。
「宣帝遊苑,樂而忘歸,遂建廟以祀,號曰樂游。」
出典:『漢書・地理志』
宣帝が苑(その)に遊び、楽しみのあまり帰るのを忘れた。そこで廟を建てて祭祀を行い、「楽游」と名づけた。
この「樂而忘歸(楽しんで帰るを忘る)」は、中国古典で“理想郷”や“心の安らぎ”を表す常套句でもあり、のちに「楽不思帰」という成語として定着しました。
つまり“帰ることさえ忘れるほどの幸福な場所”
それが「楽游原」という名の語源です。
古代中国では皇帝が心を安めた地は神聖視され、その後も貴族や文人が「理想の遊楽地」として訪れる伝統が続きました。
時代ごとの変遷
- 秦・漢時代:一帯は「宜春苑」と呼ばれる王室の庭園地で、春の行楽地として知られた。
- 前漢宣帝期(前74〜前49):皇帝の遊覧によって「楽游廟」建立、地名が定着。
- 隋代(開皇2年=582年):仏教寺院「青龍寺」が創建され、宗教・学問の場に変化。
- 唐代:地勢の高さと歴史的由緒から、長安随一の遊宴地として発展。
このように楽游原は「皇帝の遊楽地 → 仏教寺院 → 文人の詩会場」という形で、時代ごとに機能を変えながらも“人が憩う場所”という本質を守り続けてきました。
楽游原の唐時代の移り変わり
楽游原(らくゆうげん)は唐代には大変人気のあった場所です。それだけにこの地は「権力の舞台」から「文化の象徴」、そして「黄昏の詩情」へと様々な人たちの思惑によって姿を変えていきました。
初中期:太平公主:政治と権力の象徴
8世紀初頭、武則天の娘・太平公主(たいへいこうしゅ)はこの楽游原に壮麗な山荘を築きました。
丘の南面から曲江池を見下ろすその邸宅は、城を押し覆うほどの広さを誇ったと伝わります。
公主当年欲占春,故将台榭押城堙。
欲知前面花多少,直到南山不属人。出典:韓愈『遊太平公主山荘』
太平公主は春を独占しようと、城の外まで邸宅を広げた。
その先の花の数を知りたければ、南山のふもとまで行かねばならない
この詩に描かれるように楽游原は太平公主にとって権力の象徴でした。
太平公主は母・武則天の治世を支え、政治にも介入しながら唐王朝の頂点に君臨した女性です。

太平公主のイメージ画像
しかしその華やかさは長くは続きません。彼女の権力を恐れた玄宗皇帝によって謀反の罪で自害させられ。邸宅は没収、楽游原は王族の所有を離れていきます。
権力の極致が生んだ「春の楽園」は、滅びの前触れでもあった。
ここに、楽游原=“盛者必衰”という象徴が最初に刻まれたのです。
盛唐(李白):文化と詩の舞台
太平公主が去ったのち、唐王朝は開元・天宝の黄金期を迎えます。この時代、楽游原は政治の舞台から離れ、詩と文化の地へと姿を変えました。
李白(りはく/701〜762)をはじめとする詩人や文人たちは、曲江・慈恩寺・青龍寺とともにこの地を訪れ、詩会や酒宴を開きました。詩人たちにとって、楽游原は「都の喧騒を離れ、詩心を解き放つ場」だったのです。
李白自身が「楽游原」という地名を詩に詠むことはありませんが、彼が愛した曲江・終南山・大雁塔といった風景は、この丘からすべて望むことができました。
つまり、李白たちが詩に詠んだ「長安の春と詩会の光景」は、この楽游原からの眺望の延長線上にあったのです。
晩唐(李商隠):衰退と追憶の象徴
9世紀に入ると唐王朝は衰退の兆しを見せ始めます。この時代に活躍したのが李商隠(りしょういん/813〜858)です。
彼はかつて王族や詩人が栄華を誇った楽游原に登り、その黄昏の風景を次のように詠みました。
李商隠の漢詩
向晚意不適,驅車登古原。
夕陽無限好,只是近黃昏。出典:李商隠『登楽游原』
日が傾き、心は晴れない。憂いを抱えながら車を走らせ、古い丘(楽游原)に登る。
見渡す夕陽はこの上なく美しい。けれど、それはもう黄昏の直前の光だ。
この漢詩はこの時代の唐代の文人が愛した楽游原の雰囲気をよく伝えています。
当時の人々は玄宗と楊貴妃の時代(開元・天宝年間)を「黄金の時代」と考え、そこから約100年後の彼らの時代は政治・文化ともに華やかさを失ったと感じていました。李商隠の詩は、そうした“古き良き唐への郷愁”を象徴しています。

楽游原から長安の街を見たイメージ
→ 詩の丘(李白)
→ 哀惜の丘(李商隠)
こうして一つの風景が、百年のうちに王朝の興亡を語る舞台となったのです。
それでも唐人にとっては輝く丘
李商隠が『登楽游原』で詠んだ風景は、衰退した王朝を象徴する「黄昏の丘」として後世に知られました。
昔を偲ぶ詩人たちが哀愁あふれる詩を詠んでいいたころでも、現実に生きる唐の人々にとってこの丘は衰退の象徴ではありません。
唐代の都・長安では春の上巳節や秋の重陽節に登高する習慣があり、楽游原はその代表的な名所でした。
貴族や文人たちは詩を詠み、夕暮れの光に包まれて一日の終わりを楽しみました。庶民も花を観に登り美しい風景を楽しみました。
李商隠の詩が生まれた9世紀にも、この丘は依然として“都に生きる者が一度は登りたい場所”であり続けたのです。
青龍寺と空海
空海の修行場所は楽游原にあった
楽游原の東端に位置する青龍寺(せいりゅうじ)は、唐代の長安で仏教文化の中心でした。その名が日本にまで知られるようになったのは、ここが僧侶 空海(くうかい/774–835)が修行した寺だったからです。
長安・青龍寺 は 密教の発信地
青龍寺は隋の開皇2年(582)に創建され、唐代には名僧が多く住んだことで知られました。
特に恵果(けいか)が住職を務めた時代には密教の中心道場として隆盛を極めます。

空海が修行した青龍寺の跡地
Kcx36, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
空海の修行:唐密の伝来
延暦23年(804)、遣唐使として日本から渡った空海は青龍寺で恵果阿闍梨に教えを受け、わずか2年足らずで密教の正伝を受けます。
空海は帰国後、この青龍寺で学んだ密教を日本に伝え真言宗(しんごんしゅう)の開祖となりました。空海はやがて日本の文化や思想に大きな影響を与えます。
唐の文化にかかわる場所
興味深いのは、青龍寺が楽游原の丘の上に建てられていることです。丘の西側では文人たちが詩を詠み東側では僧が祈りを捧げる。楽游原全体が唐の精神文化に大きくかかわる土地でした。
空海も長安の詩人や学僧たちと交流、後の著作『文鏡秘府論』などに唐文化の感性を取り入れています。
青龍寺跡地に立つ空海記念碑
1982年:青龍寺跡地に西安市と日本の香川、徳島、高知、愛媛の四県が共同で青龍寺遺址に空海記念碑建立されました。同時に日本から桜千本が贈られ、現在は「桜の名所」として再整備されています。

西安市の空海記念碑画像
Liuxingy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
唐の文化人が親しんだ場所は現在、桜の名所としても親しまれています。
ドラマの楽游原は心の平穏を取り戻す場所

楽游原のイメージ画像
ドラマでの「楽游原」の意味
ドラマ『楽游原』でも都には「楽游原」という場所があり。何度か登場、重要な意味を持ってきます。ドラマの楽游原は戦いや権力争いに疲れた人たちが心の平穏を見つける象徴的な場所として描かれています。
この場所は、李嶷と崔琳たちにとって大切な節目に登場します。第11話では、李嶷と崔琳がお互いを理解し心を通わせた場所です。また物語の途中、戦で傷ついた李嶷を崔琳が看病し、二人が再び絆を深める癒やしと再生の場所にもなりました。
「終わり」ではなく「始まり」の地
そして最終回。争いが終わり世の中が安定したとき、二人は再びこの地へ戻ります。このとき、楽游原は終着点ではありません。これから始まる新しい人生を象徴する場所へと変わります。
平和を取り戻した李嶷たちは、誰もが自分だけの楽游原を見つけられることを心から願います。これこそが、この物語の伝えたかったテーマでしょう。李嶷にとっては愛する人との時間、崔琳にとっては静かで穏やかな日常、桃子たちにとっては仲間との信頼。
楽游原とは、現実の楽游原をモチーフにした、心の安らぎと希望に満ちた場所だといえます。
まとめ
「楽游原(らくゆうげん)」は唐の都・長安を見下ろす高台でした。唐の繁栄とやがて衰える黄昏の両方を見つめてきた歴史を持つ場所です。
でも、このドラマではこの名前が新しい意味を持ちます。戦や権力争いに疲弊した登場人物たちが心の安らぎを取り戻すための象徴的な場所として描かれているのです。
主人公の李嶷と崔琳にとって楽游原は特別。二人が心を通じ合いお互いを理解し合った場所。戦で傷つき再び絆を結び直した再生の場所。そして、すべてを終えて最後に立ち返る故郷のような場所です。
時代を超えた「心の安らぎ」
史実の楽游原が文明の頂点を映し出す現実の丘だったのに対し、ドラマの楽游原は人が幸せを見つけ出す「心の理想郷」と言えるかもしれません。
この物語が伝えているのは、誰もが自分だけの「楽游原」、つまり心の安らぎの場所を持っているということ。そして、そこへ帰ることができるという希望なのではないでしょうか。
FAQ(よくある質問)
-
Q楽游原は実在の場所ですか?
-
A
はい。西安市雁塔区に実在し、「楽游原歴史文化公園」として保存されています。
-
Qドラマと史実の関係は?
-
A
ドラマは架空王朝が舞台ですが。都に同じ名前の場所があります。美しい場所があり象徴的な意味を持っているという意味では史実と同じです。
-
Q李商隠の詩「登楽游原」はどんな意味?
-
A
盛唐の美しさと、その裏に潜む衰亡を詠んだ詩。「夕陽无限好、只是近黄昏」は栄枯盛衰の象徴です。
全40話のあらすじ・ネタバレまとめは → 『楽游原』あらすじ全話一覧

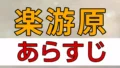
コメント