中国ドラマ「如懿伝~紫禁城に散る宿命の王妃~」最終回(第87話)のあらすじをお届けします。
乾隆帝が秋の狩りに出かけた最中に如懿が静かに息を引き取り容珮が殉死。乾隆帝は深い後悔を胸に晩年を迎えます。九年後、嬿婉も毒杯で最期を遂げ、愛と孤独の物語は幕を下ろしました。
この記事では最終回の展開と如懿が手にれた本当の自由の意味を紹介します。
※この記事はドラマ『如懿伝』のネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。
他のエピソードを見たい方は 如懿伝 あらすじネタバレ全話一覧 をどうぞ。
最終回(第87話)のあらすじ:本当の自由を手に入れる
乾隆帝は晩年に自らの白髪と如懿の髪を一つの箱に納め、緑梅が再び芽吹くのを見届けて生涯を終えました。
『如懿伝』第87話 あらすじ
木蘭秋獮と宮中の静寂
乾隆帝が妃嬪たちを連れて木蘭秋獮(狩り)へと出かけていく中、如懿は翊坤宮に残りました。
彼女は長年仕えてくれた容珮と静かに宮中を歩きます。若い頃に弘暦と無邪気に笑い合った城楼まで足を運び、遠くまで続く赤い壁を眺めながら静かに過ぎた日々を振り返りました。
その夜、庭に出て座った如懿は容珮にもそばに座るよう促します。そして、二人が初めて出会ったころの記憶をひとつひとつ語り聞かせました。
長年にわたって主人と召使いとして結ばれてきた二人の絆は、もはや言葉を必要としません。如懿と容珮はこれが静かな別れになると悟っていたのです。
(木蘭秋獮=清朝で秋に行う狩り)
回想と別れの予感
如懿は叔母の孝敬憲皇后、晞月、阿箬、嬿婉といった宮廷で関わった人々の名前を静かに口にしました。
寵愛と皇后という地位を巡る激しい争いの果てに、あまりにも多くの命が失われてしまったこと。その歳月を思い返し彼女は深く悔やみます。もし永璜や永琪が生きていてくれたなら、と涙をこぼしました。
やがて如懿は手にした茶碗を見つめ「このお茶は、もう薄くなったわね」とつぶやきます。
そして容珮に新しいお茶を淹れるよう頼むと、庭の緑色の梅を静かに見つめました。
その視線の先に、若き日の自由な青櫻がいたのでしょうか。如懿は安らかに、そっと息を引き取ったのです。
乾隆帝の悔恨と絵の修復
木蘭での狩りから宮廷に戻った乾隆帝は如懿の死を知り、深い衝撃を受けます。さらに長年如懿に仕えた容珮が殉死したという報告に言葉を失いました。
如懿の遺書には「今や自由自在」という一文が残されていました。その言葉を読んで乾隆帝は涙を流します。
彼は如懿が破り捨てた二人の肖像画を修復させよ命じました。しかし腕利きの画師はそれを拒みます。
「絵の傷は直せても、当時の真の気持ちだけは、二度と描くことはできません」
画師のこの言葉は乾隆帝にとって重くのしかかります。
乾隆帝は城壁の上で激しく泣き崩れました。彼の愛も過去も、もはや永遠に戻らないものとなってしまった事実を思い知ったのです。
9年後の結末と永遠の別離
それから9年の歳月が流れました。
あの頃の勢いを失い、すっかり老い衰えた嬿婉は側近の王蟾が差し出した毒、鶴頂紅を静かに受け入れます。
十五阿哥が正式に皇太子となり乾隆帝は重い責任からようやく解き放たれました。
嘉慶4年の冬。
乾隆帝はかつて如懿が断髪した髪を納めた箱に自分の白い髪をそっと添え。養心殿で息を引き取ります。その最期の手には二人の髪を納めた錦の箱がしっかりと握られていました。
殿の庭では如懿が愛した緑の梅が、変わらず新しい芽を出し、静かに咲き続けています。それは二人の愛の記憶が永遠に消えない象徴として残り続けたことを意味しているのかもしれません。
感想と考察
最終回は「愛と権力」がどこへ向かうのか、その答えが出ました。
如懿は皇后の座という名誉よりも自分らしく生きることを選んだのです。彼女にとって、それは自由でした。
一方、乾隆帝の胸に残ったのは「なぜ彼女をわかってあげられなかったのだろう」という、自分自身への深い後悔でしょう。
緑梅が象徴する「愛の記憶」
緑梅は、もともと如懿と乾隆帝の強い絆のシンボルでした。
それが枯れてしまったのは二人の愛が終わったことを意味します。でも再び芽を吹いた梅のように、如懿の存在や思い出は乾隆帝の心にずっと残るのです。
梅は寒い冬に花を咲かせます。だからこそ「孤高」や「純粋」な精神の象徴なのです。如懿にもピッタリな花といえますね。
晩年の乾隆帝がその梅をじっと見つめ続けました。その場面は、すべてを手に入れた権力者の孤独と取り戻せないものへの後悔が深く伝わってくるようです。
容珮の殉死が意味するもの
容珮の死は主への忠誠心というよりも「一緒に過ごした時間」の終わりを自ら選んだ行為として描かれています。
如懿の本当の孤独を誰よりもわかっていた彼女にとって主のいない宮廷にいる意味なんてなかったのでしょう。
如懿が最後に「一緒に座って」と容珮に語りかける場面は身分を超えた二人の友情が完成した瞬間といえるかもしれません。
ちなみに歴史上は殉死という習慣は当時ほとんどありませんでした。特に乾隆帝の時代から法律で禁止されていました。
なぜ如懿の葬儀は皇貴妃の格式だったのか?
ドラマ的な解釈
ドラマ『如懿伝』では如懿の葬儀が「皇貴妃」の格式で行われたのは乾隆帝が“自由な人として彼女を送りたい”と願ったからです。
彼は「如懿がもう皇后でいたくなかった」と語り、形式上は格下でも情としては最上の別れ方として描かれています。
史実はどうだった?
でも史実の輝発那拉氏(ドラマのウラナラ氏)の葬儀は決して穏やかなものではありませんでした。彼女の死後はその一族も処罰を受け、政治的には完全に失脚したと記録されています。
葬儀も皇后格ではなく、一段下の皇貴妃の待遇で行われ乾隆帝はその後も復権を認めませんでした。つまり史実では明らかに乾隆帝が怒っており、“冷遇と断絶”の象徴だったのです。
如懿が貫いた「たった一人の愛」と時代の壁
如懿が願ったのは、ただ一人の相手と向き合うまっすぐな愛でした。
ですが儒教の考え方で成り立っている乾隆帝と皇后・側室の関係は「個人だけの愛」を認めない仕組みです。愛は国を治めるルールの一つで、皇后の役目は「正しい行いや手本を示すこと」。そんな世界で彼女が抱いたひたむきな恋心は、異常なものだったと言えるでしょう。
西洋文化への憧れと脚本の工夫
制作側はそんな当時の世界観からすると非現実的な愛を「西洋文化への憧れ」という形で説得力を持たせようとしました。宣教師から聞いた一夫一婦制の話に如懿が強く心を惹かれる場面が描かれています。
この演出で彼女の理想はただの「夢物語」ではなく「新しい文化に触れた女性の憧れ」となりました。
愛の終わりではなく、心の自由
でもドラマの結末で彼女がたどり着いたのは愛が叶うことではなく、執着から解放されることでした。「自由である」という彼女の最後の言葉は、愛を失った後も心の自由を手に入れた証です。
悲劇か、救いか?
この結末を「救い」と受け取るか、「悲劇」と受け取るかは、見る人によって変わると思います。
ただ、如懿は自分が負けたとは思ってないように見えます。後宮という古い社会では自分の生き方は理解されないけれど。一人の人間として尊厳をもって人生を終えることができたのではないでしょうか。そこが最後まで執着を捨てられなかった衛嬿婉との違いだと思います。
史実のウラナラ氏とは?如懿のモデルとなった実在の皇后
如懿のモデルになった史実の清朝第6代乾隆帝・乾隆帝の継皇后について紹介します。
本当の姓は輝発那拉?
ドラマでは「烏拉那拉氏(ウラナラ氏)」となっていますが、満洲語の資料をみると本当の姓は輝発那拉(ホイファナラ)氏だったようです。
満洲の貴族・鑲藍旗(しょうらんき)出身の名門で同族からは多くの高官や妃嬪を輩出しました。
側室から皇后へ:基本はドラマと史実は同じ
如懿伝の物語同様、彼女は乾隆帝の側室から昇進し、1750年に正式に皇后の座へ。
しかし、わずか十数年後の乾隆三十年(1765年)前後、突然地位を失い、「廃后」として宮廷から姿を消しました。
史実では髪を切った理由は不明
その理由は公式記録には明記されていませんが、「断髪事件」乾隆帝への絶縁を意味する髪を切ったという逸話が伝わっています。
この行為は、満洲文化では“夫婦の決別”を意味し、ドラマの中で如懿が「筆を折る」場面の元となったと考えられています。
その後、彼女は冷遇のうちに1766年に死去。
葬儀は皇后としての礼ではなく、格下の皇貴妃扱いでした。
家臣が待遇改善を進言しましたが、乾隆帝の怒りを買って処罰されたという逸話も残ります。
ドラマのような恋愛はない
ドラマでは乾隆帝と如懿の愛がテーマになっていますが。史実ではドラマのように若い頃からの愛はなかったと思われます。
乾隆帝は輝発那拉氏に対し、亡くなった後も何ひとつ特別なことはしていません。詩を詠んでその死を悼むことさえ、しなかったのです。
ドラマと違い、史実では乾隆帝は輝発那拉氏の皇后昇進は望んでおらず、皇太后の勧めで皇后になっています。もともと乾隆帝としては気が進まなかったのかもしれません。それが悲劇の始まりだったのかもしれませんね。
詳しくはこちら → 輝発那拉氏(烏拉那拉氏)とは?乾隆帝の継皇后の実像
如懿伝の登場人物
- 如懿(にょい)/皇后 演:ジョウ・シュン
- 乾隆帝(けんりゅうてい) 演:ウォレス・フォ
- 鈕鈷祿氏(ニオフルし)/皇太后 演:ヴィヴィアン・ウー
- 海蘭(ハイラン)/愉妃(ゆひ) 演:チャン・チュンニン
- 衛嬿婉(えい えんえん)/炩妃(れいひ) 演:リー・チュン
如懿伝の関連記事
この話の前後にあたるエピソードのあらすじ感想、全話一覧記事へのリンクを紹介。ストーリー全体の流れを把握するのにお役立てください。
BS11午後1:00からの 次の放映ドラマは明蘭です。
明蘭才媛の春 あらすじ ネタバレ全話一覧紹介

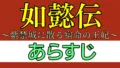
コメント