燕王 朱棣(しゅ てい)は明の太祖 洪武帝 朱元璋の四男。
後の永楽帝です。
洪武帝 朱元璋は息子たちを藩王にして各地を守らせました。四男の朱棣も国を守ることを期待されていました。朱棣は藩王になると北平(北京)を任されました。北平は元の首都・大都があった場所。そこを任されるのは期待が大きかったのでしょう。
しかし洪武帝の死後、建文帝は藩王を削減。
それに反発した燕王 朱棣は反乱を起こしました。建文帝から皇位を奪って即位します。
この記事では燕王 朱棣(しゅ てい)の誕生から皇帝に即位するまでを紹介します。
燕王 朱棣 の史実
名:棣(てい)
国:明
称号:燕王
生年月日:1360年5月2日
没年月日:1424年8月12日
日本では室町時代になります。
家族
母:孝慈高皇后 馬氏(異説あり)
妻:燕王妃 徐氏(徐達の娘。仁孝文皇后)
子供:朱高熾(洪熙帝)、朱高煦(漢王)、朱高燧(趙王)ほか。
燕王 朱棣の生涯
朱棣は 元の至正20年4月17日(1360年5月2日)。應天府(南京)で生まれました。
父は朱元璋
朱棣の父は紅巾軍の朱元璋(しゅげんしょう)。
後の明初代皇帝・洪武帝です。
母は馬氏
母は馬氏。
ところが朱棣の生母については諸説あります。
生母は違う?
明の公式資料。「明実録」「明史」では朱元璋の長男 朱標から五男 朱橚までは馬氏から生まれたことになっています。もちろん四男 朱棣も馬氏の子とされています。
ところが朱棣の母は馬氏ではない。という説も根強くあります。
洪武帝は後継ぎは嫡子でなければダメだと
「南京太常寺志」という記録には
碽妃の子:永楽帝、
孫貴妃の子:周定王 朱橚
と書かれています。「太常寺」とは皇室の儀礼を担当する部署。そこの人物が書いたのだから事実だろうというわけです。でも「南京太常寺志」は260年後
他にも諸説あります。
永楽帝も自分は嫡子だと何度も言っています。事実はどうあれ明朝としては「5人の皇子は馬皇后の子」が公式見解になっていたのは間違いありません。
父・朱元璋が皇帝になる
時は至正27年(1367年)12月。翌月の皇帝即位を控えた朱元璋は、祖廟に参拝し、7人の息子に諱を授けました。その際、四男・朱棣に与えられたのが「棣」の名です。
そして翌年、至正28年(1368年)。ついに父・朱元璋が皇帝に即位し、明が建国されました。
帝王学と武芸の鍛錬
朱棣ら兄弟は、皇帝の息子として厳しい訓練に耐えなければなりませんでした。麻の靴を履き兵士のように街外を行軍演習し、その行程の7割は馬に乗り3割は徒歩で移動することを命じられました。
さらに戦いの訓練も課せられました。
一方で朱元璋は学問も重視しており朱棣たちは儒学も学びました。
燕王の称号と北平への赴任
洪武3年(1370年)。朱棣は「燕王」の称号を与えられました。
洪武9年(1376年)。魏国公 徐達の長女と結婚。
その後、朱棣は秦・晋の二王とともに「中都」鳳陽に派遣され祖先がどのように基礎を築いたかを見学しました。
さらに三度にわたって鳳陽に派遣され兵を訓練すると同時に民の生活を深く理解することを求められました。
そして洪武13年(1380年)。朱棣は藩王として北平(現在の北京)に赴任しました。
この時、洪武帝は僧侶の道衍(姚広孝)を燕王の補佐として付けました。
燕王朱棣、モンゴルとの戦いと後継者争い
北元討伐と朱棣の武勇
洪武23年(1390年)。朱元璋は傅友徳を大将軍に任命。趙庸、曹興、王弼、孫恪らを北平に派遣。燕王朱棣の指揮下、モンゴル遠征を命じました。
燕王は傅友徳らと共に北元討伐に出発。
北元の太尉ナルブファ(乃児不花)が迤都にいることを知ると、部将の観童を派遣し降伏を勧告しました。観童は乃児不花の知人でした。観童が説得している間に明軍が元軍を攻撃。観童は逃げようとする乃児不花を説得し、燕王の陣営に招いて酒宴でもてなしました。乃児不花は燕王に降伏しました。
この勝利に洪武帝は大いに喜び、朱棣の武勇が天下に知れ渡りました。
国境警備と存在感を増す燕王
洪武24年(1391年)から洪武29年(1396年)にかけて。
洪武帝は晋王と燕王に何度もモンゴル遠征を命じました。燕王は北元の武将ソリンテムル(索林帖木兒)らを捕虜にするなど活躍しました。
洪武31年(1398年)に晋王が亡くなった後は洪武帝は燕王に北平都司、行都司、遼東都司および遼府護衛兵馬を統制させ、辺境の守りを任せました。
後継者争いと燕王の台頭
朱元璋は長男の朱標を太子に立てていましたが、秦王、晋王、燕王の間ではすでに駆け引きが始まっていました。
洪武23年(1390年)。朱棣がナルブファを降伏させた後、晋王は燕王を警戒、太子朱標に朱棣が自分の指示を無視して無茶な作戦をしたと訴えました。朱標はこの件を朱元璋に報告しました。
また朱棣が都に来ると晋王は言葉で朱棣を侮辱。燕王府内で監視を行い朱棣の「国中の細かなこと」を探ろうとしました。
太子も燕王を警戒。両者の間の緊張が高まりました。
洪武25年(1392年)。太子朱標が亡くなると洪武帝朱元璋は朱允炆を皇太孫に任命。諸王の皇位への野心を断ち切ろうとしました。
洪武28年(1395年)に秦王が亡くなり、洪武31年(1398年)には晋王が亡くなり、朱棣は諸王の中で最年長者になります。
この時点で朱棣は大きな権力と強力な軍隊を持っていました。
洪武帝は朱棣に国の守りの中心として期待する一方、その大きくなった力を警戒していました。死の直前には「諸王は都に入ってはいけない。封地の官吏や兵士は朝廷の統制を受ける」という勅命を出しました。
建文帝の藩王削減政策と燕王朱棣の反発:迫りくる戦乱の足音
洪武帝の遺産と藩王の存在
洪武帝(朱元璋)は自身と子孫の統治を盤石にするため王族男子を藩王として全国に配置しました。
これらの藩王は行政権を持たず民を直接統治することはできませんでしたが、強力な軍隊を持っていました。藩王たちは強大な軍事力で国を守る役割を担っていましたが、同時に皇帝の権力を脅かす存在でもありました。
特に燕王・朱棣は、諸藩王の中でも最大の軍事力を持っていました。
建文帝の改革と藩王の危機
建文帝は叔父たちの勢力を削ぐことが急務だと考え、藩を削る政策を強行しました。
最初に周王が廃位され、その後、斉王、湘王、代王などが次々と廃止されました。
燕王への圧力
建文帝は燕王から力を奪うため、北平に軍を派遣しました。
燕王は、建文帝の政策に危機感を募らせ、反発を強めていきました。
靖難の変勃発!燕王朱棣、ついに挙兵
建文帝の削藩政策に対し、燕王朱棣はついに反旗を翻します。
挙兵と大義名分
建文元年(1399年)7月、朱棣は北平(現在の北京)で挙兵しました。
朱棣は「君難を靖んじる」(君主の難を鎮める)という大義名分を掲げました。
その目的は、建文帝を倒すのではなく、朝廷で皇帝を惑わしている斉泰と黄子澄たちを討伐することだと主張しました。
そのためこの戦いは「靖難の変」と呼ばれます。
真の目的
もちろん、朱棣の本音は皇帝の座を奪うことでした。
黄子澄たちを批判したのは、挙兵するための口実に過ぎません。
靖難の変:燕王朱棣、皇帝の座へ
序盤の攻防
朱棣はまず通州・薊州を占領し、居庸関(長城の関門)も制圧して北平周辺の安全を確保しました。
8月、建文帝は大将軍 耿炳文に30万の兵を与えて朱棣討伐に向かわせましたが、建文帝は「朱棣を殺すな」と命じました。朱棣は雄県で官軍に勝利しましたが、耿炳文にはまだ数十万の兵が残っており、真定城に立てこもって抵抗を続けました。
朱棣は真定城を落とすことができず撤退します。
李景隆の登場と朱棣の反撃
ところが、建文帝は耿炳文を解任して李景隆を大将軍に任命しました。李景隆の無能さを知っていた朱棣はこれを喜んだといいます。
11月、朱棣ら燕王軍は北平近郊で李景隆軍を破り、李景隆は南へ逃走しました。
ここで朱棣は建文帝に黄子澄と斉泰の解任を要求。なんと建文帝は朱棣の言う通り二人を解任してしまいます。建文帝はまだ朱棣が自分の地位を狙っているとは思っていませんでした。
もちろん朱棣はこれで戦いを止めるはずもなく、建文2年(1400年)1月には蔚州と大同を攻撃しました。
膠着状態と転機
朝廷も徐輝祖(徐達の長男)らを派遣、白溝河の戦いでは燕軍も苦戦しましたが、なんとか勝利しました。
李景隆は逃走したものの斉南城を守る鉄鉉が3か月間持ちこたえました。長期戦を嫌った朱棣が軍を撤退させると鉄鉉の追撃にあって張玉が死亡するなど大きな被害を出し、徳州・滄州を奪還されてしまいます。
建文3年(1401年)。軍を立て直した朱棣は各地で官軍と交戦し勝利しましたが、燕軍が勝っても去ってしまえばまた奪還されてしまいます。
長期戦になれば物量に勝る朝廷側が有利です。戦いを終わらせるためには建文帝を引きずり下ろすしかありません。
南京攻略と建文帝の失踪
12月、南京の宦官が朱棣に有力な情報を送ってきました。洪武帝~建文帝のもとでは宦官は冷遇されていたので恨みに思った宦官が朱棣に寝返ったのです。南京の防御の弱点を知った朱棣は金陵(南京)攻撃を決定。
燕軍は途中の城は無視して一気に南京を目指しました。途中、苦しい戦いもありましたが6月には長江を渡りました。この頃には朝廷軍から寝返るものが続出していました。
朱棣は南京を攻撃。すると南京の金川門を守っていた李景隆が戦わずに朱棣に降伏、門を開けてしまいます。
燕軍が南京に押し寄せると建文帝は宮殿に火を放ちました。朱棣は配下を派遣しましたが見つかったのは皇后の焼死体だけで建文帝は見つかりませんでした。
永楽帝の誕生
建文帝が見つからないまま戦いは終わり、朝廷の機能は朱棣のものになりました。
建文4年(1402年)、朱棣は皇帝に即位し、永楽帝の時代がやってきます。
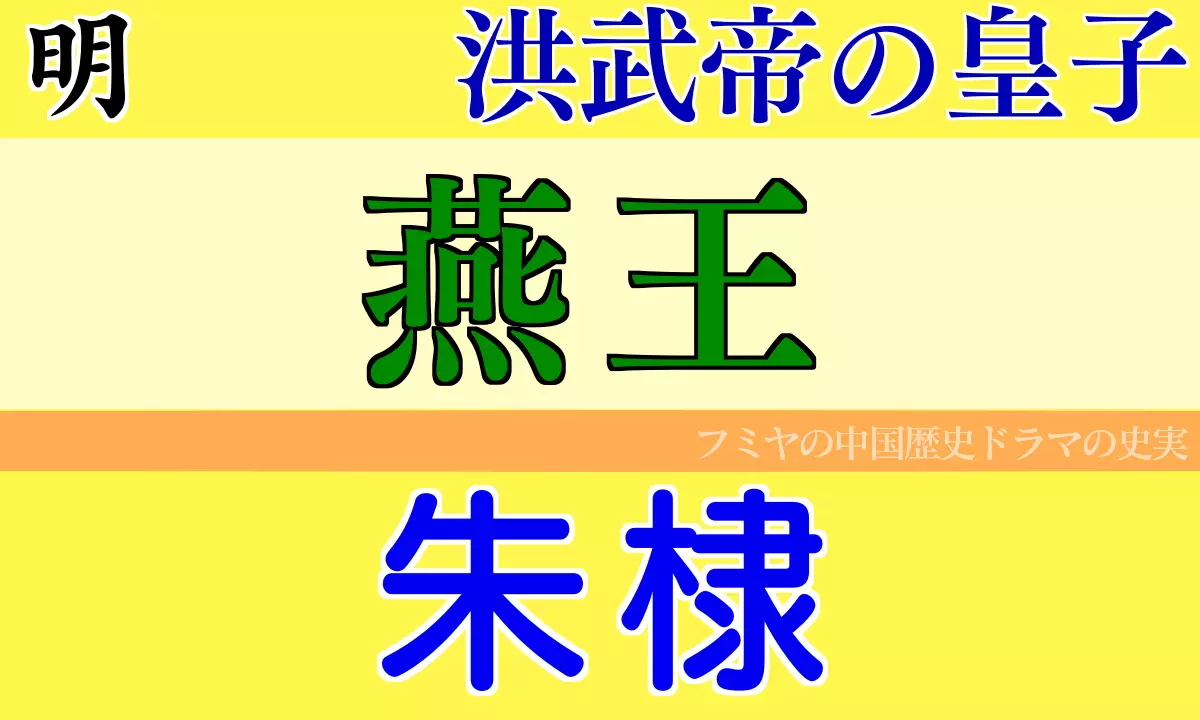
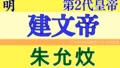

コメント