中国ドラマ『楽游原』第31・32・33・34話のあらすじをまとめました。
老鮑を失った怒りと悲しみの中で倒れる李嶷、崔琳との葛藤、新皇帝の恐れ、そして崔家軍解散の決断へと物語は大きく動きました。
この記事では 31〜34話のあらすじを紹介。皇帝が崔家軍を警戒する理由・崔家軍解散の真意・李嶷と崔琳の関係の変化 をわかりやすく紹介します。
この記事で分かること
-
新皇帝が崔琳の皇太子妃就任を拒む“政治的恐怖”の背景
-
崔家軍解散が崔倚と李嶷・崔琳に与えた心理的・政治的影響
-
柳承鋒らの偽証が皇帝の不信に火をつけ、崔家が危機に陥った経緯
-
唐〜宋に続く“軍閥と中央権力”の歴史が物語にどう反映されているか
※この記事はドラマ『楽游原』のネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。
他のエピソードを見たい方は 楽游原(らくゆうげん)あらすじとネタバレをどうぞ。
楽游原 31話 李嶷の悲しみと皇帝の恐れ
31話あらすじ:笹とんぼの願い
老鮑を失った李嶷は怒りで李崃に突進しますが、重傷で倒れ剣を振り上げた李崃にとどめを刺されそうになります。その瞬間、崔琳の矢が李崃を止め彼女は倒れた李嶷を抱えて呼びかけます。
李嶷は仲間の最期を思い出して苦しみ、何度も血を吐き崔琳に体を支えられました。
今や残った皇子は李嶷だけとなり。彼を太子にするしかありません。しかし新皇帝は李嶷の立皇太子を渋り、崔琳を皇太子妃にする案も拒みます。
崔琳は落ち込む李嶷を励まし、互いに守り合う思いを確かめました。
注目点:新皇帝が崔琳を皇太子妃に拒んだ理由は何?
新皇帝は李嶷が回復して皇太子になる流れが避けられないと理解しつつ、崔琳が皇太子妃になることを極端に嫌がりました。彼は顧相の言葉をうのみにし、崔家軍が政権に関わることを恐れたためです。
裴献が制度上の正当性を説明しても聞き入れず、皇太子妃を話題に出すのを辞めるのでした。
まして崔家は強大な軍事力をもっています。軍閥の反乱で国が滅亡しかかった直後ですから、ドラマの新皇帝が恐れるのも無理はありません。
楽游原32話 崔家軍解散への決断
32話あらすじ 新たな使命と責任
李嶷は崔琳に付き添われて青雲観を訪れ、蕭氏に皇太子擁立について相談します。
蕭氏は自分もかつて皇太子妃になることを望まなかった過去を語り、思い通りにならない人生でも悔いなく生きるしかないと諭しました。その言葉で李嶷は心の重さを少し下ろし、自分が天下の大任を引き受ける決意を固めます。
京城に戻ると李嶷は正式に大裕の皇太子となり、朝廷では皇太子妃と側室人事をめぐって議論が続きます。
崔琳と崔倚は崔家軍解散と営州帰還を受け入れますが。顧婉娘と顧相は裏で二人を引き離す策を練り始めるのでした。
注目点:崔家軍の解散と営州帰還の意味とは?
裴献は崔倚を訪ね朝議の様子を伝えたうえで、一日も早く崔家軍を解散すべきだと説得しました。崔倚も崔琳も、いずれ崔家軍が朝廷によって解体されることを理解していたので、それなら自主的に解散して営州に戻る方が傷が浅いと考えます。
崔琳は父に営州帰還を提案、自分は京城に残って外から崔家への警戒を和らげつつ、李嶷を支える役目を引き受けました。
崔家軍の解散は実質的には「軍事勢力から名門貴族への変化を描いているといえます。
楽游原33話 崔倚へ濡れ衣と崔家の危機
第33話あらすじ:巧妙な罠に落ちて
賈里は白水関の敗戦を崔倚の裏切りだと主張。新皇帝の前で嘘を重ねました。裴献と李嶷は矛盾点を一つずつ問いただしますが、柳承鋒まで嘘の報告。崔倚は一気に容疑者にされます。
新皇帝はもともと崔家軍を警戒していたため、崔倚の拘束に前向きでした。大理寺の火事で賈里が死亡すると皇帝の疑念はさらに強まり、李嶷に追跡命令を出します。
皇帝は顧相と結んで顧婉娘を良娣に封じ、皇太子妃に昇格させようとしますが、顧婉娘は自殺未遂の芝居で李嶷の同情を誘いました。
雨の中、李嶷は崔倚の無実を訴えて大殿前に跪き続けるのでした。
注目点:なぜ新皇帝は柳承鋒の理屈を都合よく信じたのか?
この回では、柳承鋒が用意周到な嘘を並べ立てたことより、新皇帝がそれを“信じたかった”ことが最大のポイントです。皇帝がもともと崔倚の軍事力と名声に恐怖を抱いていました。楽游原の世界は軍閥の反乱で一度滅びかけています。新皇帝にとって「大軍を握る将軍」は存在そのものが脅威です。
ドラマ的には柳承鋒は完全に悪役ですが、新皇帝の恐怖を利用した点は歴史の定番パターンです。彼の言ってることは嘘ですが、それ以上に「皇帝の心の弱点=功臣への不信」に寄り添っていることがポイントです。
楽游原34話 崔家軍解散の代償
第34話あらすじ:望みを叶えた代償
注目点:崔倚の一夜白頭の意味
崔倚は軍隊を解散したショックで一夜にして白髪になってしまいました。医学的には一度生えた黒髪は白くなることはありません。
医学的にはありえない現象ですが中国文化ではこの現状は「一夜白頭」といってよく出てきます。
崔家軍は代々受け継ぐ崔家の誇りで崔倚の存在意義そのもの。その軍旗を自ら降ろすのは彼の人生が終わったも同じです。髪が白くなる描写は、その衝撃の大きさを一目で伝えるための手法です。
楽游原の世界では軍閥反乱の危険性が常にある世界。崔家軍の解散は武力の時代の終わりを意味します。
崔倚の白髪化は個人の悲劇と同時に、時代の変化も象徴しているといえるでしょう。
それが嫌なら中央の政治には関わらないか、自分が皇帝になるしかない。中国では忠臣は報われない。それは歴史が証明しています。
楽游原の世界が理解できる歴史解説
軍閥で滅びた唐王朝と解体して続いた宋王朝
楽游原の今回の注目点は崔家軍の解体が大きなテーマでした。ドラマを見ていると崔家は可哀想と思いますが。中国の歴史をみているとそうも言ってられない事情があります。
ドラマの反乱のモデルとなったのは唐の「安史の乱」です。
安史の乱(755〜763)は、唐の国力を大きく奪っただけでなく、地方の節度使に強い軍事権を与える結果となりました。反乱鎮圧のために朝廷が節度使の軍事力を頼り、徴兵権と徴税件を与えたことで、戦後には地方の軍が中央の統制を受けないまま巨大化、節度使が地方の王のような存在へ変わっていきます。
河北・河東・淮南などでは節度使が自前の税収と兵士を抱え、中央からの交代命令を拒否し、部下や息子に地位を譲る“事実上の世襲”が行われました。『旧唐書』『新唐書』には、皇帝の使者が節度使に頭を下げるほど力関係が逆転した記録があり、皇帝が地方軍を抑えきれなくなっていた様子が分かります。
軍の主導権が地方にあるため、反乱が起きても中央は自力で鎮圧できず節度使同士の争いが繰り返され、中央の権威はますます弱まりました。
唐末期の黄巣の乱の頃には皇帝よりも節度使の軍が強く、朝廷はほぼ指示を出せない状態に陥ります。最終的には軍閥の一つである朱温が皇帝を圧迫し、907年に唐を終わらせました。
つまり、唐は外敵ではなく「地方軍閥」によって内側から崩れた国家でした。
この歴史はドラマ「楽遊原」の理解にも役立ちます。崔家軍のような大規模な私兵が存在すると朝廷は常に反乱の可能性を恐れなければいけません。安史の乱後の節度使と同じく、大軍を握る家は政治の主導権を奪いかねず国家の安定を脅かすからです。
唐の後に中華を統一した宋の太祖・趙匡胤が節度使を廃して武人に自前の大軍を許さなかったのも、唐が軍閥で崩れた歴史を理解していたからです。
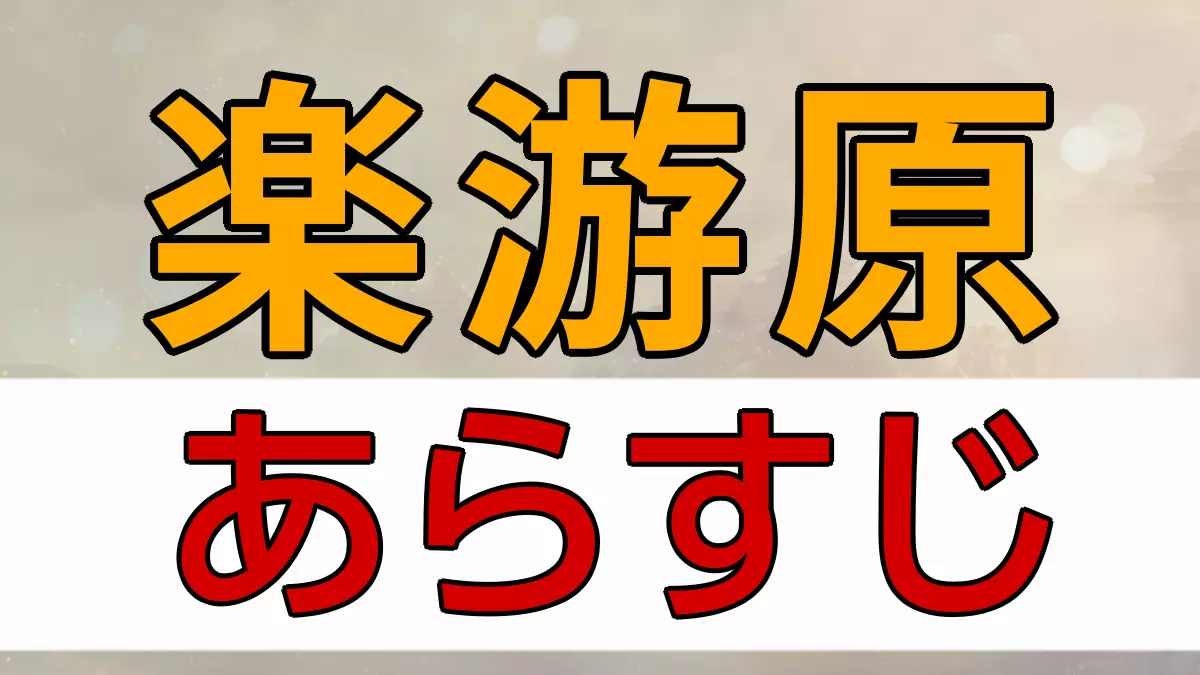
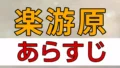

コメント