『キングダム』で知略の将として描かれる武安君 李牧(りぼく)は、史実でも戦国四大名将に数えられる天才です。
もとは北方の匈奴から趙を守る「守りの名将」でしたが、後に秦の侵攻を二度も撃退し武安君に封じられました。「無駄な血を流さない」ことを重視しますが、その有能さゆえに趙王の猜疑心を招き、奸臣・郭開の讒言(ざんげん)により、戦いの最中に処刑されるという悲劇的な最期を迎えました。
この記事では、史実の李牧の生涯・戦略・思想・死因・キングダムとの違いをわかりやすく解説します。
李牧とは?戦国末期に趙を支えた名将
李牧(りぼく)は中国戦国時代の末期に趙(ちょう)を守り抜いた名将です。
北方では匈奴を退け、西では秦を撃破し、滅亡寸前の趙を支えたことで知られます。『史記』では白起・王翦・廉頗と並ぶ戦国四大名将の一人に数えられ、その知略と忠義は今も中国史上最高の防衛将として語り継がれています。
李牧のプロフィール

李牧の肖像画
anonymous, Public domain, via Wikimedia Commons
| 名前 | 李牧(りぼく) |
|---|---|
| 生没年 | 生年不詳 〜 紀元前229年(趙王遷7年) |
| 出身地 | 趙国・柏仁(はくじん) (現在の河北省邢台市隆尧県) |
| 地位・称号 | 趙国の大将軍、武安君(ぶあんくん) |
| 主な功績 | 匈奴討伐・東胡制圧・秦軍撃退(肥之戦・番吾の戦い) |
| 家族関係 | 父:李玑/祖父:李昙/伯父:李崇/孫:李左車(軍略家) |
| 死因 | 謀反の疑いをかけられ、趙王遷により誅殺(または賜死) |
要点
- 戦国末期の趙国を支えた防衛の名将。
- 匈奴を破り、秦の侵攻を二度撃退した「守りの天才」。
- 主君の讒言により非業の最期を遂げ、趙国滅亡の契機となった。
時代背景:戦国末期の動乱と趙の苦境
趙は魏・韓とともに晋から独立した「三晋」の一国で、かつては中原最強と呼ばれた伝統国でした。
しかし紀元前3世紀に入ると北からは匈奴の脅威、南西からは新興国・秦の侵攻を受け、
国力は急速に衰退していきます。
名将・廉頗(れんぱ)や藺相如(りんしょうじょ)といった重臣を失い、内政も混乱。趙は“風前の灯”でした。李牧が活躍したのはそんな苦しい時期でした。
「史記」では李牧は辺境の地・代(だい)と雁門(がんもん)を守る武将として登場。そこで彼は匈奴を十余万騎撃破するという奇跡的な勝利を収め、趙の守りの柱として頭角を現していくのです。
人物像と評価

李牧のイメージ画像
李牧は「勇将」というより「知将」として知られます。
戦いでは焦らず敵の動きを見極めて時機を待って確実に勝つ。守備型の武将のイメージです。
日撃數牛饗士,習射騎,謹烽火,多間諜,厚遇戰士。
出典:『史記 巻81 廉頗藺相如列伝 附李牧』
毎日数頭の牛を屠殺して兵士に振る舞い、騎射を訓練させ、烽火の警報を厳守させ、多くの間諜を放ち、戦士を手厚く遇した。
とあるように。訓練や敵の襲撃に備えさせるだけでなく、兵士たちには十分な食料を与え、待遇も良くするなど。配下の者たちにも気を配れる武将でした。
「キングダム」での李牧との違い
人気漫画『キングダム』にも登場する李牧ですが、史実の彼は堅実で冷静な戦略家でした。この記事の後半では作品内で描かれる“知略の天才”李牧と、史実の将軍・李牧の違いを詳しく解説します。
まずは史実の李牧を紹介しましょう。
年表でわかる李牧
李牧(りぼく)の人生は趙国が徐々に力を失っていく戦国時代の終盤に重なります。
彼は北の匈奴との戦いから、西の強敵・秦との激しい攻防まで。20年以上にわたって趙国を支え続けた「守りの要」でした。
歴史の記録をもとに李牧の身に起こった主な出来事を時系列で紹介します。
| 年代(紀元前) | 出来事・功績 |
|---|---|
| ?年(不詳) | 李牧、生誕。出身は趙国柏仁(現在の河北省邢台市隆尧県)。姓は嬴姓、別名は李繓。 |
| (時期不明) | 趙国北部・代郡および雁門に駐屯し、匈奴・東胡の侵攻を防ぐ。堅壁清野・養精蓄鋭の方針を徹底。 |
| 前243年 | 趙悼襄王の命で燕国を攻撃。武遂・方城を攻略し、趙の北方支配を拡大。 |
| 前234年 | 秦将・桓齮(かんい)が趙を攻撃し、平陽・武城を陥落。趙は危機に陥る。 |
| 前233年 | 桓齮が再び侵攻。李牧が総司令として出陣し、肥之戦で秦軍を大破。桓齮は敗走。功により「武安君」に封じられる。 |
| 前232年 | 番吾の戦いで再び秦軍を撃破。趙国の独立を一時的に維持。 |
| 前229年 | 秦が韓を滅ぼし、趙へ三方向から侵攻。李牧・司馬尚が迎撃するも、郭開の讒言により兵権を奪われ誅殺(または賜死)。 |
| 前228年 | 秦将・王翦が邯鄲を陥落。趙王遷が捕虜となり、趙国は事実上滅亡。 |
| 前222年 | 趙の残党勢力「代国」を秦将・王賁が討伐。趙の血脈が完全に絶える。 |
李牧の戦歴ハイライト
李牧(りぼく)の凄さは、なんと言ってもその戦い方にあります。戦国時代の終わりに世の中が乱れる中、北の匈奴を打ち破り、東の燕を倒し、そして西の強国・秦を退けました。
どの戦いにも、綿密な準備と大胆な戦略が見事に組み合わされています。歴史の記録をもとに、李牧がどんな戦いをしてきたのか代表的なものを順に見ていきましょう。
代・雁門の北方防衛(堅壁清野/伺機反撃)
李牧が名将として名を馳せた最初の戦いが、北方防衛戦です。彼は代郡・雁門の守備を任され、匈奴の侵攻に対して「堅壁清野(けんぺきせいや)」と「伺機反撃(しきはんげき)」という戦略を採用しました。
無理に出撃せず、敵を消耗させる“守りの戦”を徹底。城や物資を固く守り、民を避難させて略奪の機会を与えませんでした。この慎重な方針に一時は「臆病」との批判もありましたが、李牧は動じません。
数年の沈黙の後。匈奴の油断を見抜いた李牧は20万の兵を精鋭化し、巧みに誘い込んで包囲殲滅。匈奴十余万騎を撃破し、さらに東胡・林胡をも討伐しました。これにより趙国北部は十年以上の平和を得たのです。
匈奴殲滅戦と東方諸族(襜褴・東胡・林胡)
匈奴を破った勢いのまま、李牧は東方の諸族へ矛先を向けます。まず遊牧民・襜褴(せんらん)を討ち、次いで東胡を破り、林胡を降伏させました。
これらの征討戦は単なる制圧ではなく、北辺に安定した防衛圏を築くための布石でした。
彼は現地に軍市を設け交易で物資を循環させるなど、軍政と経済を両立。これが後の「辺防体制」確立につながっていきます。
対燕遠征(武遂・方城の攻略)
北方を平定した李牧は次に東方の燕国へ遠征します。
趙悼襄王2年(前243年)、趙軍を率いて燕へ侵攻し武遂(ぶすい)・方城(ほうじょう)を攻略。これにより、燕の勢力を抑えつつ趙の北東部を強化しました。
この遠征は短期間で成功を収め、李牧の指揮力と戦略眼が宮廷で再評価されるきっかけとなります。趙国内では、もはや彼を凌ぐ将は存在しませんでした。
肥之戦(前233) 桓齮撃破と武安君封
前234年。趙は最強国家・秦の攻撃を受けました。秦将・桓齮(かんい)が趙の平陽・武城を落とし十万を斬首。趙は存亡の危機に陥ります。
翌前233年。李牧は大将軍に任命され秦軍を迎え撃ちました。戦場は肥(ひ)現在の河北晋県西方。李牧は地形を活かし、敵の進軍経路を読んで巧妙な包囲戦を展開しました。
結果、秦軍は大敗、桓齮は逃亡。趙軍の大勝は東方六国を震撼させ、李牧はその功績で「武安君」に封じられます。この戦いは、戦国史における最後の大勝利の一つとされています。
番吾の戦い(前232)再度の秦軍撃退
翌年、秦は雪辱を期して再度侵攻。王翦の指揮下で邺から北上し、番吾(ばんご/河北磁県付近)に布陣します。李牧は再び総指揮を執り秦軍を迎撃。
激戦の末、趙軍は秦を撃退し二年連続で強秦を退けるという快挙を成し遂げました。この勝利により趙国は一時的に安定を取り戻しますが、秦の執念は止まりません。
のちに郭開の讒言によって李牧が失脚すると、趙の防衛線は一気に崩壊。滅亡への坂を転がり落ちることになります。
まとめ
北方防衛で匈奴を退け、東方遠征で燕を抑え、肥・番吾の戦いで秦を破る。
李牧の戦歴はすべてが“守って勝つ”戦略の集大成であり、彼の慎重さと決断力こそが趙国を支えた真の武勇でした。
軍事思想の5本柱
李牧には戦いにおいて以下のような方針をとっていました。そこには人を動かす知恵や、国を守るための仕組みづくりといった、現代にも通じる教えが詰まっています。
① 守りを固め、経済的な自立
李牧はまず「守り」を徹底しました。敵が攻めてきても崩れない拠点を作り、そこを軍の中心にしました。さらに、その土地での商いや収入を軍費に回すことで、国のお金に頼らずに戦える仕組みを作りました。経済と防衛を一体にした戦略です。
② 無駄な戦いはせず、備えを最優先
のろしを使って敵の動きをすぐに伝える仕組みを作り、早めの対応ができるようにしました。敵が強いときには無理に戦わず、城にこもって兵を守る。あえて動かず、後で勝てるチャンスを待つ。「守って勝つ」方針を貫きました。
③ 兵を育て、やる気を引き出す
李牧は兵士の育成にも情熱を注ぎました。毎日欠かさず訓練を行い、待遇も良くする。成果を上げた者にはしっかり褒美を与える。こうして兵士たちは「この人のために戦いたい」と思うようになり、最強の守備軍へと成長していったのです。
④ 現場の判断を信じる
戦場では一瞬の判断が命取りです。李牧は「現場を見ている将軍こそが判断すべきだ」と考え、王に対しても自分の判断で動ける権限を求めました。遠く離れた場所から出た命令よりも実情を優先するその姿勢は、リーダーのあるべき姿を示しています。まさに「事件は現場で起きている」を実践した武将と言えます。
⑤ 守って誘い、機を見て攻める
李牧の戦い方は、ただ守るだけでもただ攻めるだけでもありません。まず守りを固め、わざと弱く見せて敵を油断させ、機を見て一気に反撃する。歩兵・騎兵・弓兵を見事に連携させ、敵を罠に誘い込んで撃破したのです。
まとめ
李牧の軍略は時を超えて今にも通じる知恵です。「無駄を省き、人を信じ、チームで動く」これは現代の組織や社会でも変わらない成功の原則といえるではないでしょうか。
李牧の最期と死因:諸説を比較
李牧の最期は戦国史に残る大きな悲劇の一つです。匈奴にも秦にも敗れなかった名将が、なぜ味方に殺されたのでしょうか?
『史記』や『戦国策』には、いくつかの説が残されていて、「これだ」と断定できる決定的な証拠がありません。
そこで、ここでは残された資料をもとに「郭開説」「韓倉説」「悼后説」の三つを比べてみて、本当の理由を探っていきましょう。
① 郭開の讒言により誅殺された説(最有力)
最も広く知られているのが、権臣・郭開(かくかい)の讒言による誅殺説です。
『史記・廉頗藺相如列伝』『戦国策・趙策四』に書かれた伝承では、
秦は趙王の寵臣 郭開(かくかい)に賄賂を渡し「李牧と司馬尚が秦と組んで国を裏切ろうとしている」という偽の情報を流させたのです。
趙王はこの「離間策」をあっさり信じました。すぐさま李牧を将軍から外し趙葱(ちょうそう)と顔聚(がんじゅ)に軍の指揮を交代するよう命じます。
しかし李牧は不当な命令を拒否しました。そのため趙王はひそかに兵を送り込み、彼を捕らえ斬首(あるいは賜死)させたのです。
趙の防衛線は瓦解し、翌年、秦将・王翦が邯鄲を陥落させます。
- 要点まとめ
- 出典:『史記』『戦国策』
- 原因:秦の離間計+郭開の賂
- 結末:誅殺(または賜死)
- 評価:最も史実性が高いとされる
② 悼后・春平君が関与した宮廷陰謀説
『列女伝』には、異なる筋書きが示されています。
それによると、趙王遷の母である悼后(とうこう)が秦の賂を受け取り、寵臣・春平君と通じて李牧の誅殺を促したというもの。
この説は、当時の趙王が若く宮廷内の勢力争いが激しかったことを反映しています。
政治的な腐敗と外部勢力の干渉が重なり、忠臣が犠牲となったという構図です。
ただし、この記述は道徳的教訓を含む後世の脚色の可能性が高く、歴史学的には補説的扱いになります。
- 要点まとめ
- 出典:『列女伝』
- 原因:宮廷内の腐敗と秦の賂
- 特徴:寓話的要素が強い
③ 韓倉の讒言による賜死・自決説(戦国策・秦策五)
もう一つの異説として、寵臣・韓倉の讒言による賜死説があります。
『戦国策・秦策五』では韓倉が李牧の功績を妬み、趙王に「宴席で李牧が匕首を隠して王を害そうとした」と讒言したと記されます。
王命を受けた韓倉は李牧を呼び出し罪を言い渡します。李牧は自らの潔白を訴え、義手だと説明しますが、韓倉は聞き入れません「王命になる賜死」を言い渡します。
李牧は涙を流しながら宮廷を後にし、門外で剣を口にくわえて自らの首を貫いた。
という壮絶な最期が描かれています。
- 要点まとめ
- 出典:『戦国策・秦策五』
- 原因:韓倉の嫉妬と讒言
- 結末:賜死を命じられたことよる自決
- 特徴:物語的・伝承的要素が強い
各説の比較と史料的評価
| 説名 | 主な出典 | 概要 | 歴史的信頼性 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 郭開讒言説 | 『史記』『戦国策』 | 秦の工作+郭開の裏切り | ★★★★★ | 最も有力な説 |
| 悼后・春平君説 | 『列女伝』 | 宮廷内の陰謀劇 | ★★☆☆☆ | 道徳的脚色あり |
| 韓倉讒言・自決説 | 『戦国策・秦策五』 | 寵臣の妬みによる賜死 | ★★★☆☆ | 物語性が強いが伝承的価値あり |
結論
最も史実性が高いとおもわれるのは「郭開の讒言による誅殺説」です。この説は複数の史料で一致しており、その直後に趙が滅亡している史実との整合性も高いです。
『キングダム』の李牧:史実とのギャップ
漫画『キングダム』に登場する李牧は、史実の「防衛の名将」から一歩踏み込み、
知略と理想を兼ね備えた“中華の預言者”のような存在として描かれています。
趙国の「三大天」の筆頭であり、彼が動けば国が動く。そんな絶対的な知将です。
「キングダム」ではどのように描かれているのか紹介します。
性格の違い
『史記』では「慎重で冷静、決して無謀な戦をしない名将」と記されています。理性的で現実主義者の印象です。
『キングダム』の李牧は知略とカリスマに満ちた“理想の知将”として描かれています。史実よりも人間的なドラマ性が強く、内面の哲学や信念、仲間との絆を重視する描かれ方になっています。特に龐煖(ほうけん)との出会いを通して“道”を求める精神性が付与されているのは、完全な創作です。
龐煖との関係は架空
史実では李牧と龐煖に交流があったとは書かれていません。
『キングダム』では龐煖と出会い精神的に影響を受ける場面が描かれていますが、これは物語上の演出です。
雁門での匈奴戦は史実どおり
李牧は北方の「雁門」「代」「雁門関」などの防衛を任され、匈奴の侵攻を防いだ名将でした。最初は戦わずに守りを固め、敵を油断させてから反撃して大勝。という戦術も、史実と一致します。
『キングダム』と史実が一番良く似ている部分がここです。
王騎との戦いは創作
『キングダム』で李牧が「六大将軍・王騎を討ち取る」という名シーンは完全な作り話。史実では王騎という将軍は不明な点の多い武将ですが。李牧が趙の宰相になる前に王騎を倒したという史実はありません。
ただし趙が秦の将軍を打ち破る記録(紀元前244年の戦い)は残っており、それをモチーフにした可能性はあります。
李牧の最後は?
史実の李牧は最後の時期(紀元前230年代)に秦と戦い、
・宜安の戦いで秦将・桓齮(かんき)を破る
・その後、趙王(幽繆王)の奸臣・郭開の讒言で処刑される
という流れです。
『キングダム』では趙の終盤の戦いが非常に長く描かれ、脚色の多い部分です。李牧が秦統一を阻む最後の希望として英雄的に扱われています。
現在原作漫画では秦との戦いが大詰めを迎えており、李牧の最期はまだ描かれていません。今後も秦との戦いが続くことになりますが。その過程で李牧も命を失うのかもしれません。
それが味方の裏切りによる処刑なのか戦場での戦死なのかはわかりません。
評価と影響:後世に残した遺産
李牧(りぼく)は、戦国時代末期に趙を支えた最後の名将です。その戦略と思想は後世に影響を与え、「忠義と知略の象徴」として語り継がれています。
彼は白起らと並ぶ「戦国四大名将」の一人で、最強の秦軍を二度も退け、趙国の独立を守った「唯一、秦を止めた男」でした。
勇敢なだけの武人ではなく、防衛、情報、経済を統合した「総合防衛システムの創設者」であり「守って勝つ」が彼の持ち味でした。
彼の非業の死は「忠臣の悲劇」として後世に残り、宋代以降の史家は彼を「国を支えた忠勇の士」と称えています。彼の「守りの哲学」は、後代の兵法や辺境政策に大きなヒントを与えました。
関連記事
戦国七雄や始皇帝まわりの流れを、さらに立体的に理解したい方は、気になるテーマから下の記事もチェックしてみてくださいね。

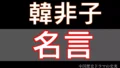
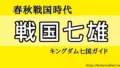
コメント