中国ドラマ『灼灼風流』のタイトルを見て「読み方は?」「意味は?」と疑問に思ったのではないでしょうか?
この記事では、『灼灼風流』の正しい読み方「しゃくしゃくふうりゅう」と、ドラマのヒロイン像にぴったりの意味「型にはまらず輝く才能」について詳しく解説します。古典での使い方も紹介してタイトルの深い意味まで理解できますよ。
「灼灼風流」の読み方
『灼灼風流』は日本語で 「しゃくしゃくふうりゅう」 と読みます。
日本語ではあまり耳にしない言葉ですよね。
これは「灼灼」と「風流」を繋げた造語です。なので「灼灼」と「風流」の意味を知ればタイトルの意味も分かるのです。
次にいったいどんな意味があるのか紹介しましょう。
「灼灼」の意味と史実での使われ方
「灼灼(しゃくしゃく)」は、明るく輝く、キラキラしている様子を表す言葉です。
- 「灼」は単体でも「明るく輝く」という意味
- 「灼灼」と重ねると光や輝きがさらに強調されます
『灼灼風流』の「灼灼(しゃくしゃく)」は中国古典でもよく使われています。
若く美しい花嫁の祝福を願った『詩経』の例
中国最古の詩集『詩経・周南・桃夭』には次の一節があります。
桃之夭夭,灼灼其華。
(桃はやわらかく、灼灼としてその花は美しい)
これは詩経でも有名な漢詩です。この詩は若く美しい娘が嫁いでいく様子を若々しい桃の木にたとえて、その幸福と家庭の繁栄を祝う歌です。
ここでの「灼灼」は花が鮮やかに輝き咲いている様子を表しています。華やかさや生命力を感じさせる表現ですね。

強い日差しを表現した『詠懷八十二首』
『詠懷八十二首』にも「灼灼」の表現が見られます。
灼灼西隤日,餘光照我衣
(輝き燃えるような太陽が西に傾き、その残光が私の着物を照らしている。)
これは魏晋時代の文学者で阮籍(げんせき、210-263年)の漢詩。
この場合は照り付ける太陽の明るさや光の強さを強調する言葉として使われています。
この漢詩の状況は晴れやかな状況を詠んだ「桃之夭夭」とは正反対。
曹魏の末期、司馬氏による王朝乗っ取りが進む中、それを食い止めようとした者たちが次々と命を失っていく、そんな悲しく悔しい思いを詠んだ歌の中に登場する部分です。
ここでは物悲しく沈んでいる本人とは正反対に、強烈な西日が照らしている様子を描いています。

灼灼まとめ
古典では「灼灼」は花や光の美しさ、鮮やかさ、光の強さを表現します。
『灼灼風流』での「灼灼」も、主人公の個性・知性・存在感の輝きを象徴する表現といえますね。
「風流」の意味と史実での使われ方
「風流」の意味は広い
「風流(ふうりゅう)」は、日本語では雅や風情を指し。中国・韓国時代劇では定職につかず遊び歩いている人の生き方を意味することもありますが。中国古典では人物の性格や生き方を表す言葉として登場します。
特に文学や詩では才能や見た目、型にはまらない生き方を表す際に登場します。いくつか具体例をみてみましょう。
李白が尊敬する人を詠った「贈孟浩然」
吾愛孟夫子、風流天下聞。
(私は孟浩然先生を愛してやまない。その風流ぶりは天下に名高い。)
この詩は唐の詩人・李白(りはく、701-762年)が尊敬する先輩の詩人 孟浩然(もうこうねん、689-740年)のために詠んだものです。
この時代の「風流」は、後の時代の「風流」よりも幅が広く権力や富に執着せず、俗世のしがらみを離れて自由な精神性や生き方を指す場合が多かったようです。
李白はそのような生き方をしていた孟浩然を心から尊敬して、この詩を贈ったのです。

山で孟浩然を思い出す李白
李白「對酒憶賀監」
次も李白の漢詩「對酒憶賀監」から。
四明有狂客、風流賀季真。
長安一相見、呼我謫仙人。
(四明山に風変わりな人がいる、その風流な人こそ賀季真である。長安で彼に会った時、私を「天上から流されてきた仙人」と呼んでくれた。)
ここで李白が「風流」と称えたのは、唐代の詩人である賀知章(がちしょう、659- 744年)です。彼は高齢でしたが、俗世にとらわれず酒を好み自由奔放な言動で知られていました。李白はそのような賀知章の生き方を「風流」と表現、尊敬していました。また賀知章が李白のことを「謫仙人」(天から追放された仙人)と呼んだという逸話も有名。
この詩は二人の友情の深さを表現したものです。
蘇軾「念奴嬌·赤壁懷古」
北宋の時代の詩人・政治家 蘇軾(そしょく、1037-1101念)が三国志の赤壁の戦いを詠んだこの詞も有名です。
大江東去、浪淘盡、千古風流人物
(長江(大江)は東へと流れていき、その大いなる波が歴史上の英雄(風流人物)を洗い流してしまった)
ここでは「風流人物」という形で使われています。三国時代の英雄たちが、世俗の名声や富に囚われず、自分の信念を貫いた生き方をしたことを意味しています。
現実の三国時代の武将たちが富や地位に無頓着だったとは思えませんが、少なくとも蘇軾はそう思っていました。そして蘇軾は英雄たちの生き方が時を超えても美しいと称賛しているのです。

赤壁でしみじみとする蘇軾
風流まとめ
風流は時代や人によってさまざまな意味がありますが。古典では「風流=雅やかなだけでなく、才能豊かで自由な生き方や個性」を象徴しています。
日本語での「風流=雅・風情」より意味が広く、人物の性格や生き方を表すことが多いです。
富や名声に執着せず自由に生きる生き方が『灼灼風流』でのヒロインにぴったり合うのではないでしょうか。
「灼灼風流」の意味とドラマとの関連
というわけで。
- 「灼灼」=キラキラ、輝く、光り輝く
- 「風流」=自由、個性豊か、型破り
「灼灼」はヒロイン・慕灼華の知性・個性・存在感の輝き。「風流」はそれまでの常識や価値観に縛られない型破りな才能や生き方を表現。
この二つを合わせると慕灼華の「キラキラとした才能あふれる自由な生き方」という意味になります。
まとめ
『灼灼風流』の読み方は「しゃくしゃくふうりゅう」。
古典でも「灼灼」は光や花の輝き。「風流」は型破りで才能豊かな自由な生き方を象徴する表現です。ヒロイン像やドラマのテーマにぴったりですね。
| 言葉 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 灼灼 | しゃくしゃく | 明るく輝く、キラキラしている |
| 風流 | ふうりゅう | 型にはまらず、才能が優れ常識にとらわれない |
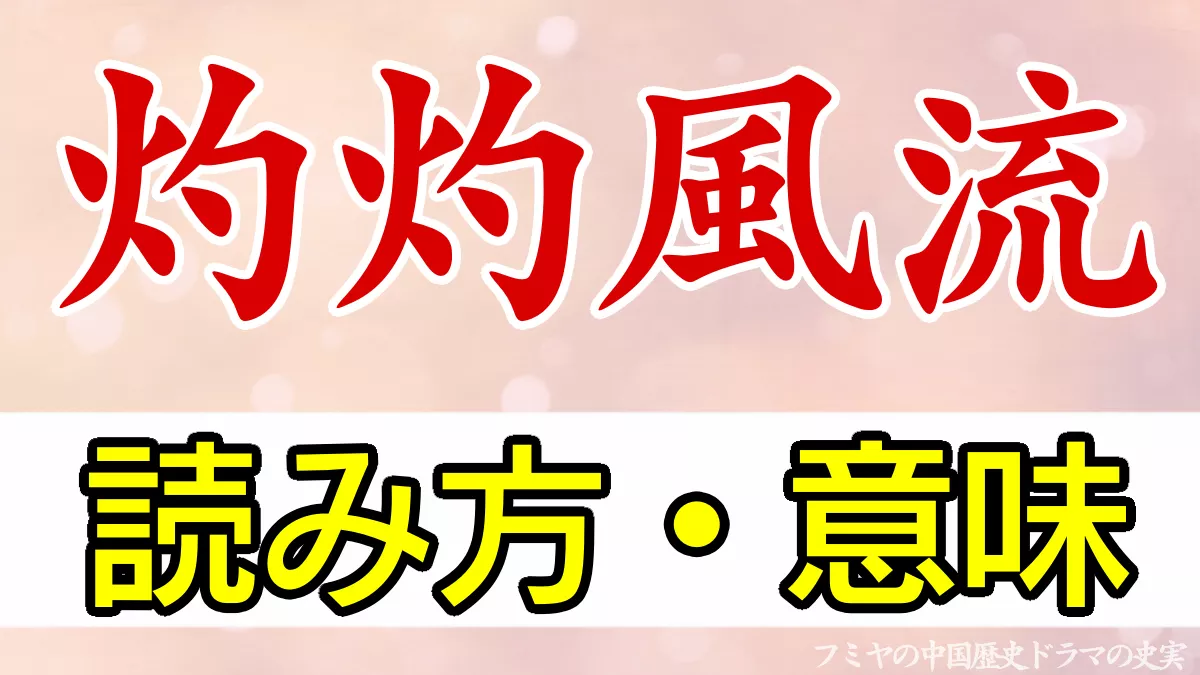

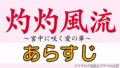
コメント