中国ドラマ『灼灼風流』を見ていて、「科挙って本当にこんな試験だったの?」と思った方も多いのではないでしょうか。
作中で描かれる「女子科挙」や「状元・探花」といった称号は史実とどこまで同じで、どこからがドラマならではの演出なのでしょうか。
この記事では『灼灼風流』の科挙の仕組みをわかりやすく整理して史実との違いや見どころを解説します。
「灼灼風流」で描かれた 試験科目・三段階の試験制度・女子受験の真偽・殿試の順位呼称 までまとめて紹介します。
ドラマ『灼灼風流』で描かれる科挙のしくみ
中国ドラマ『灼灼風流』の序盤では科挙はドラマの大きなテーマとして描かれています。
ドラマの科挙は歴史的な科挙制度をベースにしていますが、ドラマに合わせて脚色されています。ここではドラマの中では科挙はどのような仕組みになっているのか整理してみましょう。
郷試(きょうし):地方試験
郷試は全国各地で実施される試験です。ここに合格しなければ中央の試験を受ける資格は得られません。ドラマの中では郷試の描写は省かれていますが、主人公はすでに合格している設定なので最初から優れた人物だとわかります。
実際には郷試を受ける資格を得るためにも試験があって簡単にはいきませんが。ドラマではそういった制度があるのかどうかもわかりません。
郷試は明・清時代では3年に一度行われていました。劇中ではどの程度の頻度で行われているのかまではわかりません。
郷試に合格した人は「挙人」と呼ばれ、庶民よりも一段上の地位になります。史実では会試に合格できなくても地方の役職につくこともできますが。ドラマの挙人にどの程度の特権があるのかはわかりません。
会試(かいし):都での本試験
郷試を突破した「挙人」は翌年に首都で行われる会試に挑戦します。こちらも3年に一度です。
ドラマでは試験当日に会場に入って即日試験が行われる形で描かれています。試験科目は次の3つです。
- 経書:諸子百家の思想の理解度を問う(史実では儒教の四書五経が中心)
- 詩文:テーマに沿った漢詩を作る
- 時事:社会問題に対して意見を述べる(史実の「策問」に相当)
史実の策問は長文の政策論文を提出するものでしたが、ドラマでは即興の質疑応答や討論形式にの「時事」に脚色され、映像的にわかりやすく工夫されています。
会試に合格すると「貢士」と呼ばれます。
殿試(でんし):皇帝の最終審査
殿試は科挙の最終段階で皇帝が自ら臨む特別な試験です。といっても不合格になることはなく、最終的な順位を決める場とされています。合格者の序列は皇帝の裁量で決まります。
『灼灼風流』では慕灼華が殿試で妨害を受けますが、持ち前の機転で切り抜けて女性として初めて「探花」に選ばれるという展開になっています。
三魁(さんかい)
殿試の上位三名には、以下の称号が与えられました。
- 状元(一甲第一名)
- 榜眼(一甲第二名)
- 探花(一甲第三名)
これらは唐〜宋代に成立した慣習的な呼び名で、正式な官報では「一甲第一名」などと記されました。清朝では1万人以上の受験者のうち、進士になれるのはわずか数百名。その中の1位〜3位は大変な名誉です。将来を期待される人材とされ、それなりに良い役職に就くこともできました。
『灼灼風流』の科挙は宋時代をモデルにしているようなのでもっと受験者が少ない可能性は高いですが。それでも名誉なことには違いありません。
「進士」になると朝廷の役職に就くことができる、税や労役を免除される、王朝(宋)によっては軽い罪なら刑罰を受けないなどの特権が与えられました。
ドラマではどの程度の特権があるのかわかりませんが。貴族でない者が朝廷の役人になるには「進士」になるしかないと描かれているので、史実に近い待遇なのでしょう。
試験科目とドラマ演出の特徴
『灼灼風流』の科挙試験は、史実の科目を参考にしていますが。ドラマならではの演出がされています。そのためドラマとしても十分楽しめる内容になっているのです。
経書(諸子百家)
史実では儒教経典に限定されました。ドラマでは諸子百家に拡大されています。儒教が強調する「女性は家に従うべし」という価値観と、女子科挙の設定が矛盾するので変更されていると考えられます。
ドラマでは慕灼華が諸子百家の知識を活かして一か所も間違うことなく回答していました。彼女の知識と暗記力を表現する示す見せ場になっています。
暗記力の高さを調べる科目として設定されているようですね。
詩文(文学的表現力)
唐代には重視された科目。ドラマでは「黄花」をテーマに多くの受験者が「菊」を選ぶ中、慕灼華は出題者の意図を読み取って、より適切な詩を作りました。漢詩の技術も必要ですが劇中では「何を読み取り、どう表現するか」が重視されているように描かれていました。
時事(討論・即興問答)
史実の策問をアレンジした科目。長文の政策論文ではなく質問に答える形式として描かれています。
ドラマでは出されたテーマに対して「辺境を養って平和を保つ」と斬新な回答をして、高い評価を得ました。常識にとらわれない発想も必要とされているよです。
歴史(史実)との違い・共通点と相違点
『灼灼風流』の科挙は、史実をもとにしていますが、ドラマを盛り上げるために大胆な脚色が加えられています。ここでは実際の科挙との共通点と違いを紹介します。
共通点
- 三段階の試験(郷試→会試→殿試)という構造
- 試験科目に「経書・詩文」が含まれる点
- 合格者の呼称(挙人・貢士・進士)
- 殿試の上位称号(状元・榜眼・探花)
違う所
- 女性の受験:史実では不可能だが、ドラマの中心テーマとして導入。
- 日程:史実では数日間にわたり実施されたが、ドラマでは1日で完結。
- 経書の内容:儒教に限定されず、諸子百家全般を対象に変更。
- 時事問題:史実の策問は長文論述だが、ドラマでは討論形式にアレンジ。
まとめ
『灼灼風流』は今までなかった女子科挙の存在する世界が描かれています。そこでヒロイン・慕灼華は自立して自分の夢をかなえるために科挙に挑みます。
史実では男性だけが受験できた科挙ですが。あえて女性が挑戦できる設定にしたことで、社会の常識や性別の制約をわかりやすく描かれています。
制度では許されているのに、反対されたり、偏見を受けたりする。それは現代にもつながる問題かもしれません。
関連記事
ドラマ「灼灼風流」をさらに楽しむにこちらの記事も用意してあります。
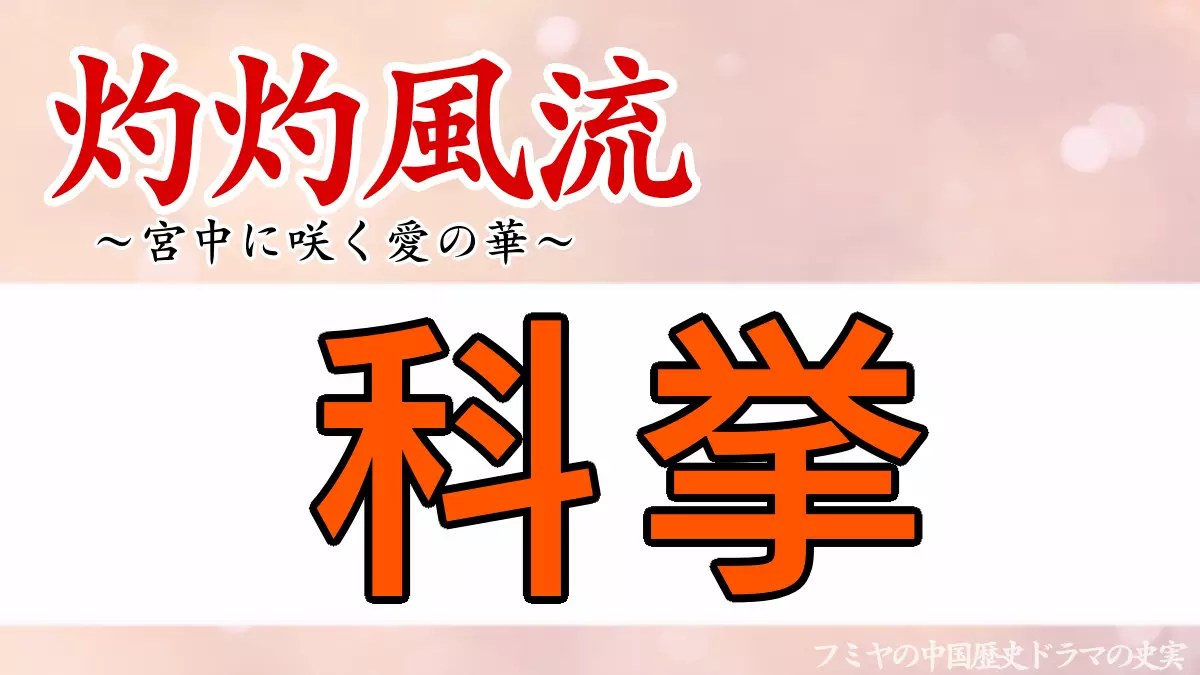

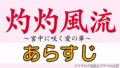
コメント